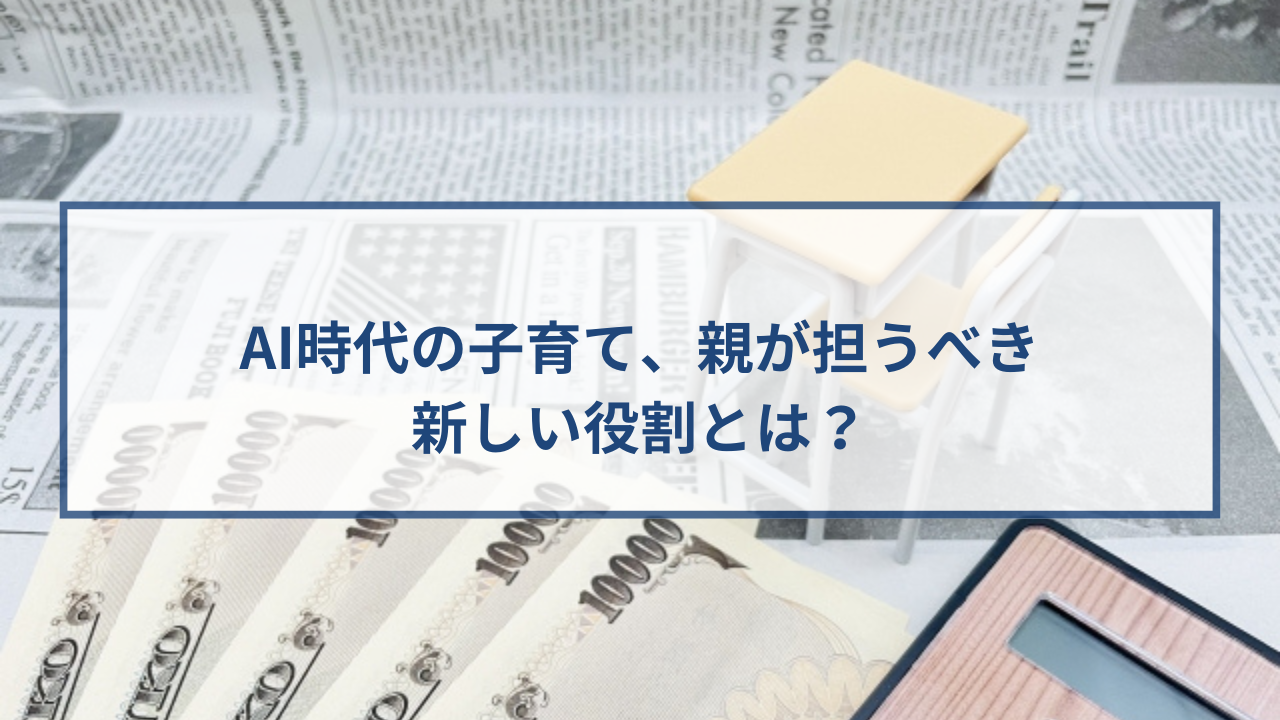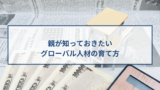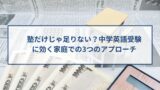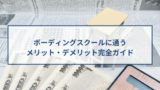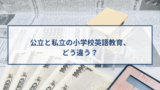「昔と同じ子育てでは通用しないのかもしれない」。
そんな不安を抱える親御さんが、近年急速に増えています。
スマートフォンやタブレットが子どもの生活の一部になり、AIがおもちゃや学習ツールに組み込まれる今。親御さんがかつて経験した子ども時代とは、まったく異なる環境が子どもたちを取り巻いています。
「子どもにどんな力を身につけさせれば良いのか?」
「親として、どう接すれば将来困らないのか?」
これらの問いに一つの正解を見つけるのは、もはや難しい時代です。
それでも、親御さんにできることはあります。
それは、「これからの社会で必要とされる力」を理解し、子どもと一緒に学び続ける姿勢を持つことです。
今回は、AI時代の子育てにおいて親が担うべき新しい役割について考えていきましょう。
AI時代に変わる「学び」と「子育て」

かつて、子どもの情報源は限られていました。親や学校の先生、本やテレビが中心で、情報は大人から「与えられる」ものでした。
しかし現代では、子どもたちはSNSや動画、アプリなどを通じて世界中の情報にアクセスできます。
さらに、AIが質問に答え、学習をサポートするのが当たり前になりました。
情報の受け手だった子どもたちが、情報の選択者・発信者に変わっているのです。
学校教育も「正解主義」から「探究型」へ
文部科学省が進めるGIGAスクール構想により、小学校からタブレットを使った授業が当たり前になっています。
さらにプログラミング教育が必修となり、「正解を求める」よりも「問いを立て、考える力」が重視されるようになりました。
中学や高校では探究型学習(PBL:プロジェクト・ベースド・ラーニング)が広がり、正解のない問題に取り組む授業が増えています。
親御さん自身が受けてきた「知識暗記型」の教育とは、大きく異なる世界が子どもたちを待っているのです。
親が果たすべき新しい3つの役割

このように、教育のスタイルが大きく変化する中で、親としてどのような役割を担うべきかが次の課題となります。
親が果たすべき新しい3つの役割を挙げます。
- 情報リテラシーのナビゲーター
- 挑戦と失敗を支える応援者
- 共感と協働の育成者
それぞれ解説します。
情報リテラシーのナビゲーター
AIは情報を提供しますが、その情報が正しいかどうかまでは判断してくれません。
親御さんの新たな役割は、子どもが接する情報の「選び方」を一緒に考えるナビゲーターになることです。
たとえば、SNSで得た情報について「どうしてそれを信じたの?」と子どもに問いかけたり、「誰がその情報を出しているのか」を一緒に確認する習慣をつくることができます。
この対話を重ねることで、批判的思考(クリティカルシンキング)が自然と育まれます。
将来、膨大な情報の中から必要な情報を取捨選択できる能力は、学びだけでなく人生全体を支える大きな力となります。
情報リテラシーを育むのは、特別な教育プログラムではありません。
日々の何気ない会話の中で、親御さんが情報の背景や意図を一緒に探る姿勢を見せることが何より重要です。
しかし、情報を選べるようになるだけでは足りません。次に大切なのは、「行動する力」と「失敗を恐れない心」を養うことです。
挑戦と失敗を支える応援者
AIは最適解を示すことができますが、人間は挑戦と失敗の経験を通じて成長する存在です。
現代の教育でも、「失敗を恐れず挑戦する力」が重視されています。
しかし、結果を重視する文化が根強い中で、子どもが安心して失敗できる環境を整えるのは簡単ではありません。
親御さんの役割は、結果よりもプロセスに目を向け、挑戦そのものを認めることです。
「うまくいかなかったけど、最後までやり抜いたのはすごいよ」
「次はどうしたいと思っている?」
こうした声かけが、子どもの自己効力感(自分にはできると思う力)を高めます。
最近では、探究学習やプロジェクト型学習を取り入れる学校や、英語を使って探究するインターナショナルスクールが増えています。
こうした教育機関は、「挑戦と失敗」を実践的に学ぶ場として注目されています。
もちろん、すべての家庭で利用する必要はありませんが、家庭の方針や子どもの個性に合うなら、選択肢として検討するのも良いでしょう。
挑戦を支え、情報リテラシーを育む。
そしてもう一つ、これからの時代に欠かせないのが「人と協力し、共感する力」です。
共感と協働の育成者
AIはどれほど賢くなっても、人間の「感情」や「共感」を理解することはできません。
共感力と協働力は、これからの社会で人間にしかできない重要なスキルです。
家庭では、子どもの感情を受け止め、言葉にして共有することが大切です。
「悲しかったんだね」「悔しかったんだね」と親御さんが気持ちを代弁することで、子どもは自分の感情を理解し、表現できるようになります。
また、兄弟や友達、学校の仲間との違いを受け入れ、尊重する姿勢を日常的に示すことも重要です。
共感と協働を育むために、異文化理解や国際交流の経験も役立ちます。
最近では、英語環境で多様性を学べる探究型スクールやプログラムも増えてきました。
「英語を学ぶ」だけでなく、「違いを理解し、協力する力」を自然に身につける場として、多くの親御さんに選ばれています。
このように、AI時代の子育てでは親御さんの役割が大きく変わっています。では、これからの家庭教育はどのような姿勢で進めていくべきなのでしょうか。
親も「共に学ぶ」存在に

これまでの子育てでは、親は「正解を知っている存在」として子どもに道を示してきました。
しかし、今の時代は正解そのものが変わり続ける社会です。
親御さんも、「知らないことは子どもと一緒に学ぶ」という姿勢が求められています。
新しい知識やスキルに挑戦する親の姿を見せることで、子どもたちは「大人も学び続ける」という価値観を自然に受け入れるようになります。
必要に応じて、英語教育や探究型の学びなど、家庭だけでは得られない教育リソースを無理のない範囲で取り入れることも、親子の成長を支える手段となります。
AI時代の子育ては、正解を探すことではなく、親子で学び続けるプロセスです。
焦らず、一歩ずつ。
今日できることから始めていきましょう。
情報の選び方、挑戦と失敗に向き合う心、そして共感と協働する力。
この3つを大切にしながら、親子で未来の学びを楽しんでいければ、それが何よりの教育になるはずです。