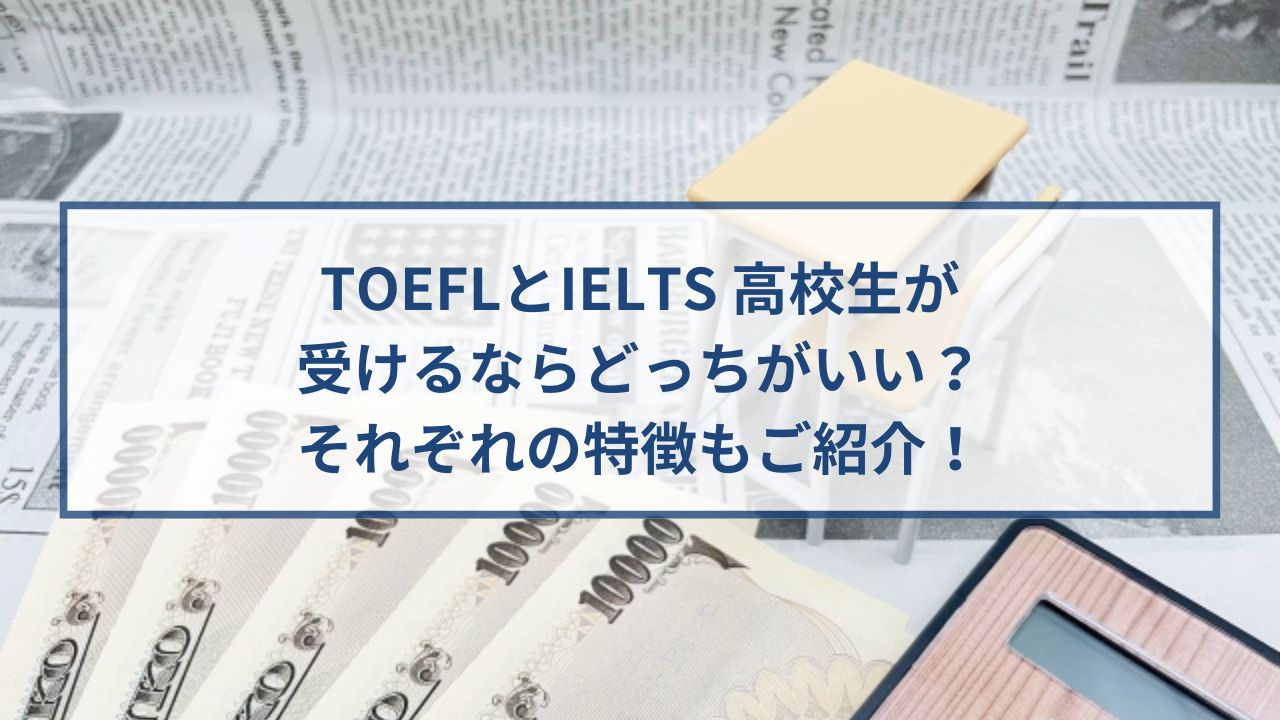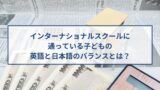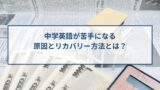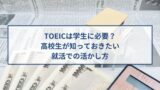「高校生でも準備しやすいのはどっち?」「効率よく最短でスコアを出す道筋を知りたい」
同じ4技能(読む・聞く・話す・書く)を測る試験でも、TOEFLとIELTSはテストの空気がけっこう違います。
だから、やみくもに勉強を始める前に「自分が取りやすい土俵」を選ぶのが先。ここでは、高校生が迷わず一歩を踏み出せるように、最新の形式・時間・受験環境の違いを押さえつつ、英語力タイプ別のフィット感や準備の進め方まで、解説していきます。
まずは全体像

最初に知っておくと迷いが減るのが「所要時間」「各セクションの配分」「受験方法(会場/自宅)」の三つ。
ここだけ押さえておくと、勉強計画の骨格が一気に組みやすくなります。TOEFL iBTは現在約2時間で4技能を連続実施する設計。
内訳はリーディング約35分、リスニング約36分、スピーキング約16分、ライティング約29分で、チェックインを含めると2.5時間ほど見ておくと安心です。
公式が時期区分でフォーマット(2026年1月21日以前/以後)を明示しているので、受験日に近いページで確認しておくと確実です。
一方、IELTS Academicは合計2時間45分。会場受験でもオンライン受験でも基本の配分は同じで、リスニング→リーディング→ライティングを続けて受け、スピーキングだけ同日か前後7日以内に別枠で面接官と対面(もしくはオンライン)で行う運用が一般的です。
受験スタイルの柔らかさ
TOEFLには自宅で受けられるHome Editionがあり、機材・通信・試験環境などの要件を満たせば受験が可能。チェックリストや当日の流れも公式で細かく公開されています。学校や部活で土日の移動が難しい高校生にとっては、選択肢が増えるのが助かるところです。
IELTSの注目点はOne Skill Retake。4技能のうち伸ばしたい技能を60日以内に1回だけ再受験できる仕組みがあり、エリアや実施機関により提供状況は異なるものの、面接で「うまく話せなかった」などのピンポイントな敗因を挽回しやすいのが魅力です。
内容と空気感

両試験とも4技能を測りますが、読解・聴解の題材や、書く・話すで求められる文脈が少し違います。TOEFLは大学講義やキャンパスライフを背景にした素材が多く、ノート取り→要旨把握→統合タスク(読む+聞く→書く/話す)といったアカデミック運用の比重が高め。試験時間がコンパクトになった分、集中のギアを途切れさせずに走り切る設計です。
IELTSは、リーディング・リスニングは日常から学術まで幅広く、スピーキングは面接官との1対1。身近な話題から意見を述べる流れが組まれており、対人コミュニケーションの自然さがスコアに反映されやすいのが特徴です。学術目的ならAcademicを選択(General Trainingは就労・移住向け)という住み分けも明確です。
スコアと受入れ
受入れで悩む必要はあまりありません。TOEFLもIELTSも、世界中の大学・機関で広く認められています。TOEFLは200以上の国・地域、13,000以上の機関で受入れと公式が明言。更新が入ることがあるので、出願校の公式要件ページと併せて都度チェックするのが安全です。
IELTSも同様に、英語圏・非英語圏を問わず大学出願の王道テスト。特に英国・オセアニア圏では根強い採用実績があり、近年は北米でも多くの大学がIELTSを標準受入れ。出願前に志望大学の「English proficiency」欄を直接確認するのが鉄則です。(スコア可否や最低要件は学部で異なるため、必ず大学サイトを確認しましょう。)
どっちが自分向き?高校生の得意・苦手から逆算する

形式を知ったら、いよいよ自分ごとに落とし込む段階です。ここでは、英語のタイプ別に「TOEFL向き/IELTS向き」の目安を、勉強のしやすさという観点で言葉にしていきます。もちろん例外はありますが、スタート地点の目安としては実用的です。
読む・聞くが得意、学校の授業でノートを取るのが苦にならないタイプ
TOEFL寄り。講義調の文章や、複数情報を統合して答える設問に抵抗が少ないはず。スピーキング・ライティングの統合タスク(読む→聞く→要約して話す/書く)も、普段から社会や理科の授業で「要点→説明」の癖がある人はフィットしやすい。最新の短時間フォーマットは集中力勝負なので、模試で“2時間走り切る”感覚を早めに作っておくと伸びやすいです。
対面で話すと伸びる、身近な話題なら言葉が出やすいタイプ
IELTS寄り。面接官との会話形式で温度感がつかみやすく、言いよどんでも立て直せる余白があります。One Skill Retakeが使える会場なら、苦手技能だけ再挑戦も可能。作文はグラフ・図表の要約(Task 1)→意見論述(Task 2)の型がはっきりしているので、テンプレに頼らず“構成の骨”を先に作る練習が効きます。
準備のロードマップ

試験選びが決まったら、勉強は「取れる点の順」に並べ替えるのが早道です。ここからは、TOEFL派・IELTS派それぞれの初動2か月の回し方を、学校の勉強と両立できる分量で言語化します。
TOEFL派
平日:教科書レベルのアカデミック英文を1日1パラ、チャンクで前から読み、要旨を1文にまとめる。週2回は講義音声を使ってシャドーイング→ディクテーションを5分だけ。
週末:リーディング1セット+リスニング1セットを通しで解いて「2時間集中」の筋力を養う。
スピーキングはテンポ命。15秒準備→45秒回答の“時間管理”をメトロノームのように体に入れる。
ライティングはIntegrated(要約)→Independent(意見)の順で、まずは構成メモを正確に切る練習から。公式の現行配分は短時間集中型なので、時計と仲良くなるほど強いです。
IELTS派
平日:Speaking Part 1の身近テーマを毎日2トピック、30秒×2本を録音。週2回はPart 2の1〜2分スピーチで理由→例の二段構成を口で組み立てる。リーディングは設問タイプ(True/False/Not Given、Matching、Sentence completionなど)の見極め練習を短時間で回す。
週末:Writing Task 1(図表要約)は比較表現と増減表現のストックを作り、Task 2(意見論述)は主張→理由2→結論の3段だけでまず書き切る。スピーキングの日程が本試験と別日になる可能性もあるため、模試は「本番さながらの順番(LRW→S)」で経験しておくと安心です。
受験の実務

どちらの試験を選んでも、最後は大学側の要件に合わせるのが本筋。スコアの有効期限、提出方法、必要最小スコア(総合と各技能)、試験方式の可否(自宅受験・オンライン成績の扱い)、再受験制度の認知など、細かい条件は大学・学部で差があります。特にスピーキングの配点比重や1技能だけ再受験の合算可否(IELTS One Skill Retakeの扱い)は大学のスタンスに依存するため、必ず公式の出願ページで確認を。TOEFL/IELTS公式の受入れ情報は目安として便利ですが、出願直前の判断は大学サイトが最終ソースです。
会場か自宅か、いつ受けるか
部活の大会・定期テスト・修学旅行…高校の年間行事はぎっしり。会場までの移動時間、午前型か午後型か、Home Edition(TOEFL)の要件を満たせる静かな部屋の確保など、生活に沿って“事故らない日”を先にブロックしておくと本番の集中度が上がります。自宅受験は便利な反面、通信・機材・本人確認の要件が厳格なので、チェックリストを読み込んで事前テストを必ずやる、これだけで当日の不安はぐっと減ります。
まとめ

TOEFLは学術運用の密度で攻めやすく、IELTSは対話と表現の自然さを出しやすい。受入れはどちらも広いので、最初の一歩は「自分が点を取りやすい土俵」を選ぶこと。
・講義調の素材や統合タスクに強い→TOEFL
・面接形式で話すと伸びる、図表要約や意見文の型が好き→IELTS
受験スタイルは、TOEFLのHome EditionやIELTSのOne Skill Retakeといった制度も上手に使い、部活や学校行事とぶつからない勝てる日程を組む。最後は志望校の要件ページで細部をすり合わせる。ここまでできれば、あとは走るだけです。あなたの英語は、正しい土俵と順番で、ちゃんと点になります。