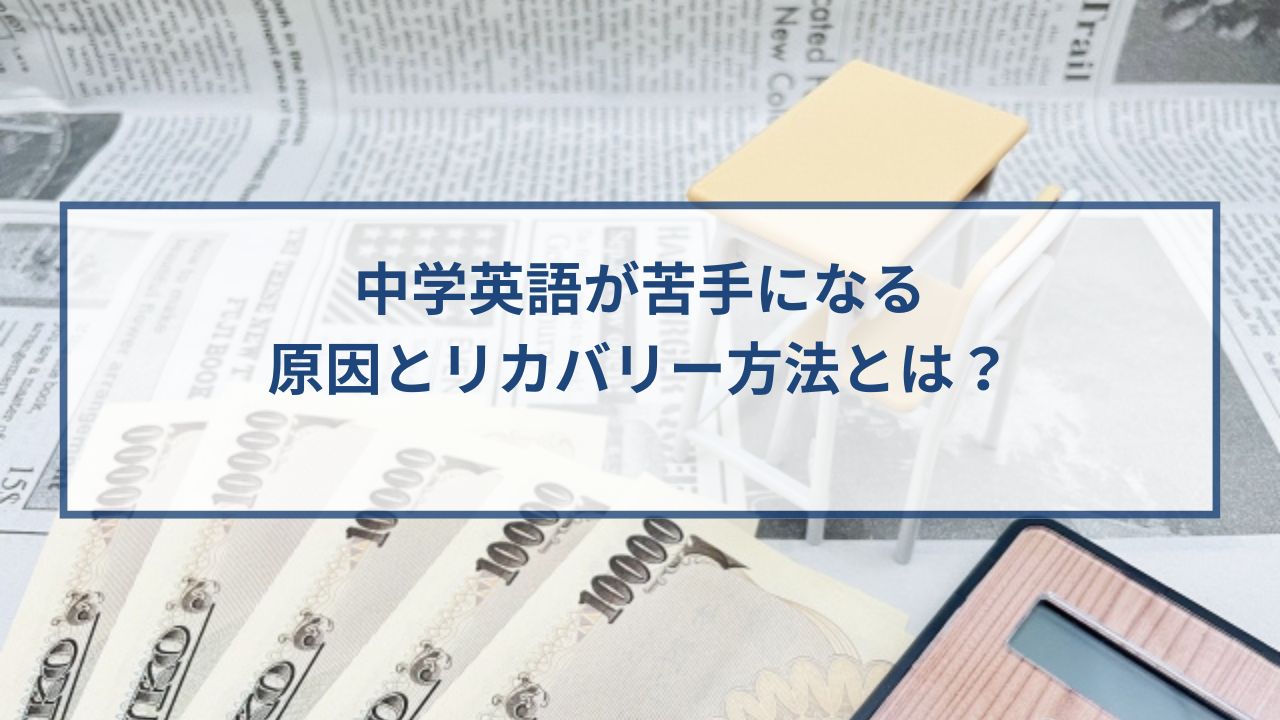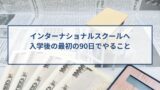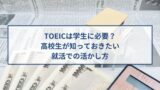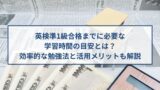「文法の説明はわかったつもりなのに、並べ替え問題で毎回つまずく」「何から手をつければいいのか分からず、英語だけ置いていかれている気がする」
中学の英語は、小学校の慣れから積み上げの教科にガラッと変わります。覚える量も増え、授業のテンポも上がり、定期テストでは「読んで、考えて、書く」を短時間で求められる。
苦手に感じるのは自然なことです。ここでは、つまずきやすいポイントを優先順位でほどきながら、今日から戻せるリカバリーの具体策をまとめます。勉強時間を増やすより、順番とやり方を変える。その切り替えだけで、英語は意外なくらい戻ります。
まず原因を見つける

英語の苦手は「センスがない」ではなく、土台のどこかが欠けているだけ。やみくもに単語を増やしても、土台が整っていないと点は伸びません。最初に「何が足りないか」を見極めると、やることは半分に減ります。ここでは、定番の原因を聞く・読む・文法・書くに分けて、症状と対処の入口を整理します。自分に当てはまるところに印をつける気持ちで読み進めてみてください。
音が拾えない
英文を聞くと全部がひとかたまりに聞こえる。これは単語力の前に、英語特有の音のつながりや弱形に耳が慣れていないサインです。
音読とシャドーイングで「音の切れ目」を体に入れると、一週間でも聞こえ方が変わります。意味が分からなくてもまずはマネして口を動かす。これが最短ルートです。
読むのが遅い
一語ずつ訳して止まるクセがあると、長文で時間切れになります。英語は「かたまり」で前から処理する言語。名詞句・動詞・前置詞句を前からスライドするイメージで目を動かす練習をすると、辞書なしでも読める範囲が広がります。
返り読みをやめるだけで、本文理解と設問対応の両方が軽くなるはず。
文法が点でバラバラ
be動詞/一般動詞、三単現、時制、助動詞、前置詞…と個別に覚えると迷子になります。文法は「SVO」の軸に何を足すかの発想で整理。
まずは現在形・過去形・進行形の三本柱を一本化し、そこに助動詞や前置詞句を付け足すだけ。軸が決まると、並べ替え・整序・英作の迷いが一気に減ります。
書けない
頭では分かっていても、手が止まる。これは出力の練習不足。スピーキングと同じで、書くのも筋トレです。短文を毎日3行、主語・動詞・目的語だけでいいから書き切る。完璧な英作は不要。まずは「英語で3行出せる自分」を作るのが先です。
リカバリーの基本設計

原因が見えたら、やることはシンプル。はじめの14日は「戻す期間」。音・語順・時制の土台を短時間で回し、その後に伸ばすへ。時間は毎日30〜40分で十分。大切なのは、毎日同じ順番で積むことです。ここからは、家で自力で回せるミニルーティンを、実際の流れに沿って置いていきます。
前半7日、音と語順の再起動(毎日15+15分)
前半は音読→シャドーイング→チャンク読みの3点セット。音読は教科書本文を2段落、区切りにスラッシュを入れて前から声に出す。続けて音声を流し、1文遅れで重ねるシャドーイングを1周。最後に本文を見ながら、名詞句/動詞/前置詞句のかたまりに線を引く。意味より前から処理するを脳に覚えさせる週です。
後半7日、文法の軸と3行英作(毎日10+10+10分)
S(主語)V(動詞)O(目的語)を現在形・過去形・進行形に入れ替えるドリルを10分。次に、助動詞can/will/mustだけを足して10分。最後に3行英作を10分。I played soccer yesterday./I am doing homework now./I will visit my grandparents. のように、時制を入れ替えるだけでOK。1日1セットで英作への恐怖が消えていきます。
スコアを上げる技術

点数は「知識」×「手順」。同じ実力でも、手順が整うとテストで落ち着いて力を出せます。ここでは、長文・リスニング・文法問題の順に、得点の取り方を短くまとめます。大げさなテクニックではなく、すぐ真似できる現実的な動き方です。
長文読解:設問→本文→根拠マーキング
先に設問をざっと見て、問われ方のタイプ(内容一致/語句補充/並び替え)を確認。本文は段落の最初と最後の文を丁寧に、真ん中はチャンクで前から滑らせて読む。根拠になりそうな場所にうすく線。戻る前提で読み進めると、焦りが消えます。語句補充は直前直後の言い換え表現がヒント。長文は「全部理解」ではなく「設問に答えるために必要なところを取る」競技です。
リスニング:先読み→メモ→聞き逃しは捨てる
選択肢と設問は先に目で処理。固有名詞・数字・時刻だけメモの欄に準備しておく。聞こえなかった一文に固執すると次も落とします。割り切って次のヒントを待つ。最後の設問ほど情報が新しいので、後半に集中力を残す配分が有効です。
単語・文法・書く力の日々の回し方

知識はストック、スキルは循環。毎日すべてをやる必要はなく、軸だけ回せば十分です。ここでは、3つの要素を週で回す設計を紹介します。忙しい部活生でも回る分量にしています。
単語:1日10語×ピラミッド暗記
新出10語を見て→声に出して→例文を1つ読む→夜に3語だけ書く。翌朝、昨夜の3語を口で言ってチェック。覚える順は「声→目→手」。すべて書かないから続きます。土日は5日分の抜け語だけ復習。穴だけ埋めるから効率が高い。
文法:時制タワーと助動詞セット
ノート1ページを縦に三分割して、現在・過去・進行の3段タワーに。同じ文を時制だけ入れ替えて並べる。そこに can/will/must を付け替え、否定・疑問も1回ずつ。文法は「見開き1枚に集約」がコツ。テスト前はこの1枚を見るだけで軸を思い出せます。
書く:3行ジャーナル
テーマは日常でOK。I played…/I learned…/I will… の3行セット。スペルが怪しい単語は別語で置き換えて前に進む。止まらずに書き切る体験が“出力の筋力”を作ります。週に1回だけ先生役の家族がチェックし、主語と動詞のズレだけ直せば十分。
メンタルと習慣

成績は感情の影響を受けます。できる実感がないと、机に向かうまでが遠い。続けるための小さな仕掛けを、家と自分に用意しましょう。ここでは、今日から置ける現実的な工夫を二つ。
タイマー×場所固定
勉強は「やる気」より「準備の少なさ」。机の上は教科書・音声端末・シャーペン・赤ペンだけ。タイマーを12分にセットしてスタート。終わったら2分だけ片づけ。この“開始と終了の儀式”があると、毎日がルーティンになります。
小さな見える化
音読した回数をカレンダーに○、3行ジャーナルを書いた日は☆。印が増えるだけで脳は報酬を感じます。友だちや家族と写真で共有すると、さらに続きやすい。成果はテストの点だけじゃない。日々の○と☆が“戻っている証拠”です。
まとめ

中学英語の苦手は、才能ではなく設計の問題。
①音と語順を前半7日で再起動、②文法の軸と3行英作を後半7日で定着、③テストは手順で取りにいく。
単語は声から、文法は1枚に、書く力は3行から。大きな努力より、小さな継続。やることを細く短く、でも毎日。
今日の12分の音読と、今夜の3行でいい。次の定期テストで「読めた」「書けた」が一つ増えたら、それがもうリカバリーの合図です。焦らず、でも止まらず。英語は必ず身につきます。