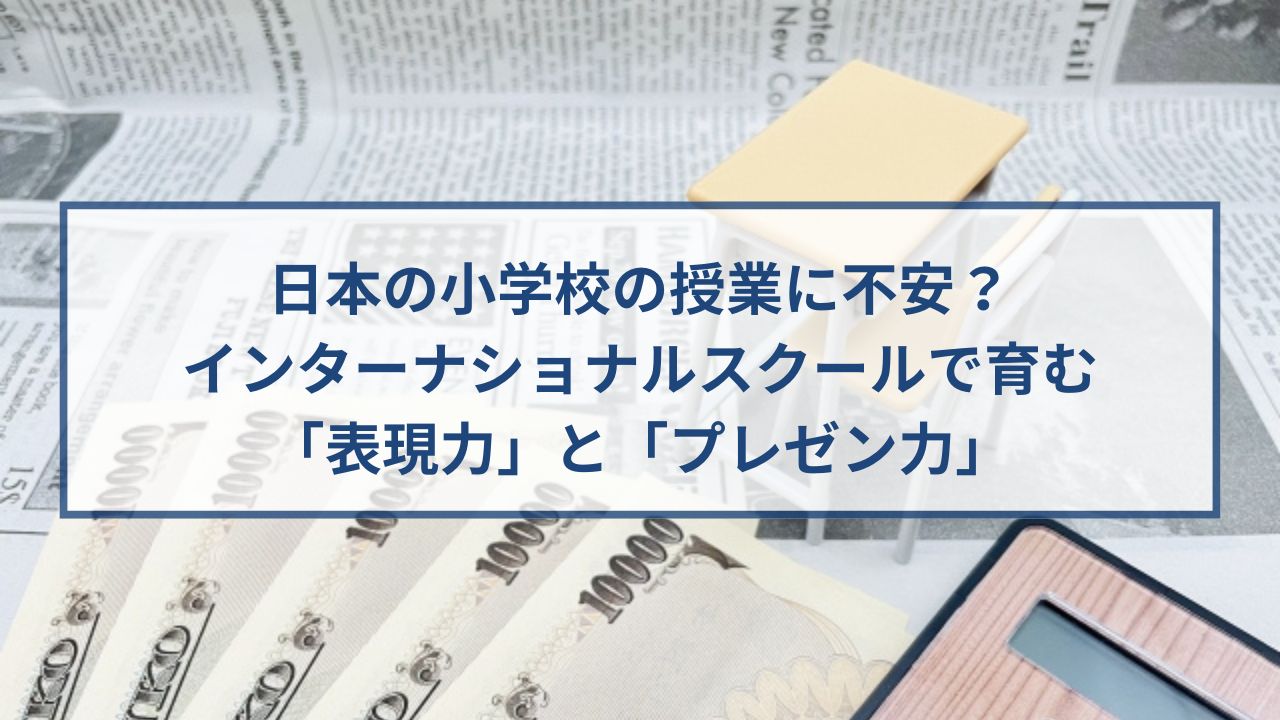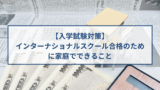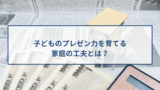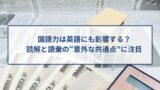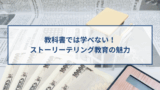「うちの子、ちゃんと自分の考えを言葉にできるようになるのかな…?」
そんな風に思ったことがある親御さん、少なくないと思います。日本の小学校では、知識の定着や集団行動が重視される場面が多く、「自分の意見を述べる」「相手に伝える」といった力を育む機会は、まだまだ少ないのが現状です。
近年、社会では自分の考えを伝える力=プレゼン力や表現力がますます重視されており、その育成は学校だけに任せられない時代になっています。そんななか、注目されているのがインターナショナルスクールという選択肢です。
英語力だけでなく、ディスカッションや発表、プレゼンテーションを日常的に経験できるカリキュラムは、「考える力」と「伝える力」を同時に育ててくれます。
なぜ、今表現力が注目されているのか?

以前であれば、「話すのが苦手でも、コツコツ頑張れば大丈夫」と思われていた時代。しかし、AIの進化やグローバル化が進んだ今、「ただ知っている」だけでは社会で活躍しづらくなってきました。これからの子どもたちに求められるのは、「自分で考え、それを相手に伝え、共感を得る力」。つまり表現力やプレゼン力こそが、生きる力の軸になっていくのです。
実際、企業の採用現場や大学のAO入試などでも、論理的に話す力やプレゼンテーション能力が重視される場面が増えてきています。また、SDGsや多様性を学ぶ場面でも、自分と違う価値観をもった相手と“対話”しながら進めていく力が問われます。
こうした背景から、子どものうちから「安心して表現できる環境」でトレーニングしていくことの大切さが見直されているのです。
インターで育つ「伝える力」のベースとは?

インターナショナルスクールでは、授業のなかに自然と「話す」「伝える」「聞く」が組み込まれています。朝の会でのスピーチ、小さなグループでのディスカッション、図工や理科の発表会まで、「人前で話す」経験があらゆる場面にちりばめられているのです。
たとえば、小学校低学年の子どもたちでも「Show and Tell(ショー・アンド・テル)」という活動が行われています。これは、自分の好きなものや体験をクラスメイトの前で紹介し、質問を受けるというシンプルな発表活動。しかし、そこには「自分で選ぶ→構成を考える→相手にわかりやすく伝える→質疑応答でやりとりする」という、プレゼンの基本要素がすべて詰まっています。
こうした日常的な積み重ねによって、子どもたちは話すことが当たり前の行動として身についていきます。恥ずかしさを感じたり、緊張したりすることもありますが、クラスメイトや先生が温かく受け止めてくれることで、安心して挑戦できるのが特徴です。
英語でのプレゼン、どう育つ?日本との違いとは?

インターナショナルスクールでは、英語でのプレゼンテーションがごく自然な日常の一部として取り入れられています。たとえば、理科の授業で学んだ実験結果をまとめてクラスで発表したり、自分の意見をスライドにまとめてディスカッションをリードする機会が小学生のうちから与えられます。
ここで特徴的なのが、「自分の意見を持つこと」が強く肯定される文化です。日本の教育では、空気を読む・まわりに合わせることが重視されがちですが、インターでは「あなたはどう思う?」が会話のスタートになることが多く、意見の違いも“個性”として受け入れられる雰囲気があります。
また、英語でのプレゼンと聞くと「難しそう」と感じる親御さんも多いかもしれませんが、子どもたちは日々の生活のなかで自然と語彙を増やし、自分なりの表現を身につけていきます。言語の壁よりも「伝えたい思い」が先にあることが、プレゼン力を育てる本質なのかもしれません。
プレゼンだけじゃない!表現力が伸びる教科横断型の学び

インターナショナルスクールでは、表現力が「国語」や「スピーチ」の授業だけにとどまらず、すべての教科をまたいで育てられています。つまり、どの授業でも「考えを言葉にする」機会が設計されているのです。
たとえば、こんな教科横断型の取り組みが行われています:
- 理科×プレゼンテーション:観察した植物の成長記録を、写真や図と共にスライドでまとめて発表。単なる実験報告ではなく、気づきや自分なりの仮説を「自分の言葉」で説明する練習が行われます。
- 美術×ストーリーテリング:描いた絵に対して「なぜこの色を選んだの?」「どんな気持ちを表現したの?」と問われる中で、感情や意図を言語化する力が自然と養われていきます。
- 音楽×ディスカッション:作曲家の背景や楽曲の意味をグループで議論。違う感想をもつ友だちと話すことで、自分の表現に自信と広がりが生まれます。
これらの活動では、「話す力」だけでなく「感じたことを言語化する力」も育ちます。知識の習得だけではなく、感性や創造性といった“非認知能力”の育成にもつながっているのがポイントです。
表現力を育てるために家庭でできること
インターナショナルスクールのような環境でなくても、家庭の中で「表現力」の土台を育てることは可能です。特別な教材やトレーニングがなくても、日々の親子のやりとりの中に、十分な伸びしろが眠っています。
以下は家庭でできる具体的な工夫です:
- オープンな質問を投げかける:「今日は何をしたの?」ではなく「今日はどんなことが楽しかった?」「そのときどう感じた?」など、答えが一つでない問いを意識して会話に取り入れることで、子どもは“自分の言葉”で話す習慣がつきます。
- 話を途中で遮らない・急かさない:子どもが言葉を探している時間も、考えている時間です。大人が言葉を補ってしまうと、「自分の言葉で伝える機会」を奪ってしまうことにも。ゆっくりでも、自分のリズムで話せる空気を作ってあげることが大切です。
- 感情や出来事を一緒に振り返る習慣を持つ:「あの時、悔しかったんだね」「嬉しかったって言ってたもんね」といった共感の声かけは、子どもが自分の感情に気づき、それを言葉にする力を育てます。
こうした日常のコミュニケーションこそが、「話す力」「伝える力」のベースになります。家庭での会話が、表現力の第一歩になるのです。
これからの時代、「知っている」より「伝えられる」ことが武器になります。インターナショナルスクールの環境では、英語力だけでなく、表現力やプレゼン力といった“生きる力”が自然と育まれていきます。
もちろん、こうした力は学校だけで育つものではありません。家庭でも、「話す・聞く・考える」のサイクルを意識して過ごすことで、子どもたちは大きく成長していきます。
もし「今のままで大丈夫かな?」という不安があるなら、それは新しい一歩を踏み出すサインかもしれません。
ことばは、未来を切り開く力になります。 その芽を、今、家庭と学校で大切に育てていきましょう。