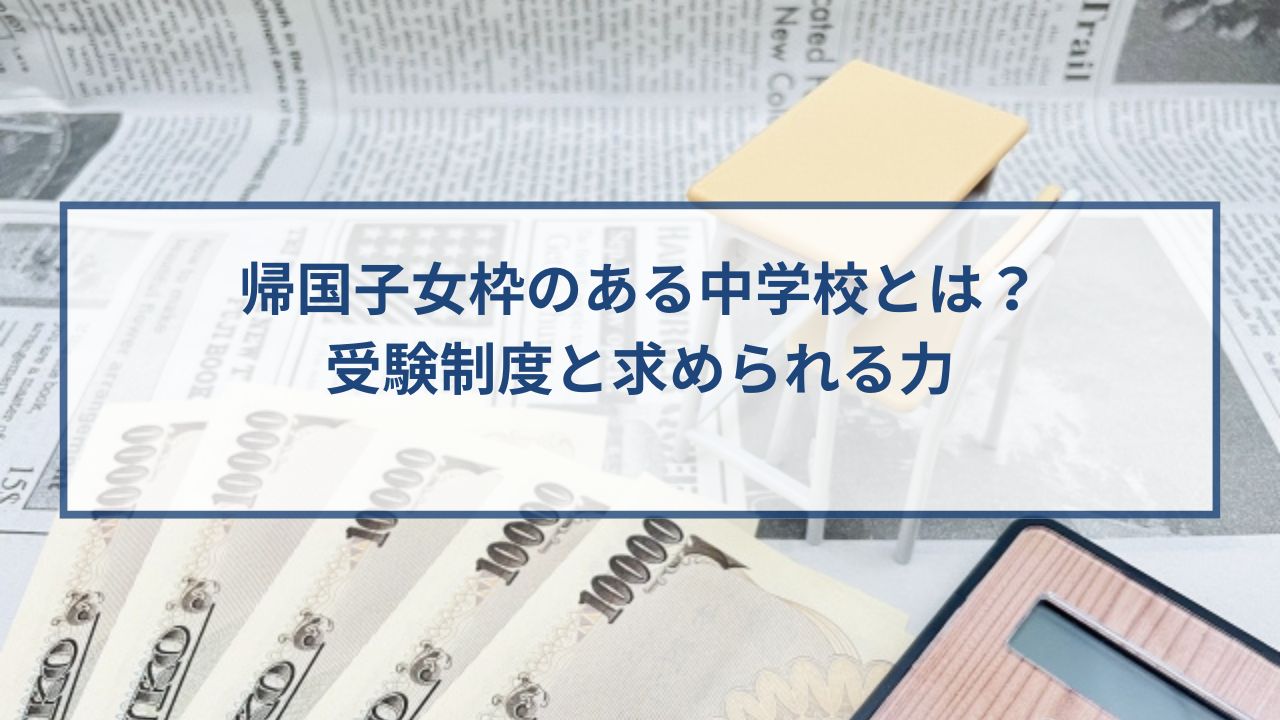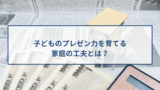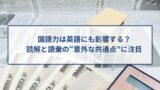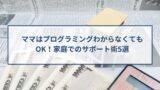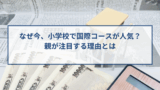「うちの子、中学受験ってできるのかな…」
日本に帰国したばかりの親御さんから、こんな声を聞くことがよくあります。海外でのびのびと育ってきたお子さん。英語は堪能、学力も申し分ない。でも、いざ日本での中学受験となると「制度がわからない」「周囲とのレベル差が心配」「そもそも受け入れてくれる学校ってあるの?」と、不安がつきまとうのも当然です。
特に、英語や探究型学習に力を入れていたご家庭ほど、「日本の詰め込み型教育にうちの子が合うのか」と悩まれる方も多い印象です。
さらに「日本語での受験は大丈夫かな?」「周囲に似た経験の子がいないと孤立しないかな…」といった、心の居場所に関する不安も、見逃せません。受験という制度的なハードルと、文化的なギャップの両方を乗り越える必要があるからこそ、早めの準備と情報収集が重要になります。
そこで本記事では、帰国子女の中学受験における制度や学校の選び方、必要とされる力、そして家庭でできるサポートまで、やわらかく、でも確かな情報をベースにお届けします。 焦らず、一緒にお子さんに合った進路を見つけていきましょう。
帰国子女枠ってどんなもの?

まず知っておきたいのが、日本の中学受験では「帰国子女枠」や「国際生入試」といった、海外経験のあるお子さんに配慮した特別枠が数多く設けられているという点です。
たとえば、以下のような学校が挙げられます:
- 慶應義塾中等部や渋谷教育学園渋谷中学校(渋渋)
→ 海外経験の長い子に対して英語力・探究力・個性を重視した選考。論理的な思考力やディスカッション能力を評価される傾向もあります。 - 広尾学園や三田国際中等教育学校
→ 帰国生クラスが用意されており、英語やグローバル教養の学びが継続しやすい。IB(国際バカロレア)をはじめとする海外式教育プログラムとの親和性も高く、英語を“使う力”として磨き続けられる環境です。 - 女子学院や武蔵中学などの伝統校でも帰国枠入試あり
→ ただし学力試験のレベルは高く、日本語での出題にしっかり対応する必要がある。基礎学力の徹底が求められ、教科書レベルを超える深い理解や応用力も重要になります。
こうした学校では、英語力を加点対象にしたり、面接や作文で「国際経験」を問うこともあります。つまり、受験自体が“日本の常識”だけでは測れない設計になっているケースも少なくないのです。
また、「入試科目が一般入試と異なる」「英語での面接がある」など、出願条件や試験内容も大きく異なる場合があるため、早めの情報収集が不可欠です。特に入試日程が前倒しで行われる「帰国枠専用入試」は、年内(12月〜1月)に行われることも多いため、タイミングを逃さないよう注意しましょう。
ただし注意点も。学校によって求めるスキルや傾向はバラバラで、英語力があっても「日本語の記述力」が足りないと落ちてしまうこともあります。「帰国枠=優遇される」と思い込まず、それぞれの学校の方針や選考内容をじっくり読み取っていく必要があります。
学校選びの際は、お子さんが「どのような学び方が合っているか」「どのような学校生活を望んでいるか」までを丁寧に対話しながら、学力だけではない軸で比較検討することが大切です。
求められる力と準備の方向性

帰国子女の中学受験では、単なる学力だけでなく、「ことばの使い分け」や「多文化理解」「自己表現力」など、複数の力が試される場面が多く見られます。これは、帰国子女がもつバックグラウンドの多様性を前提にしているからです。
リスト形式で整理すると、主に以下のような準備が求められます:
- 1. 日本語での読解力と記述力の強化
帰国枠といえども、日本語で出題される試験がほとんど。英語は得意でも、日本語の長文読解や記述に慣れていない子は不利になりがちです。日々の読書や、要約・感想文の練習が効果的です。読んだ本を親子でディスカッションする時間も、日本語での思考力・表現力を養う貴重な場になります。 - 2. 自己表現やプレゼンテーションの経験
面接や作文で「あなたの海外経験について教えてください」と問われる場面も多くあります。自分のことを日本語でわかりやすく・印象的に伝えるには、日頃から親子の対話の中で「なぜそう思ったの?」「どこが楽しかった?」と深掘りしていく習慣が大切です。 - 3. 英語力の“活かし方”を明確にする
学校によっては英語スピーキングテストやリスニング試験が課される場合もあります。そのため、英語の学習を止めるのではなく「どう活かすか」の視点が重要です。インター系スクールやオンライン英会話を続けることで、受験に直結しなくても強みとして残すことができます。
こうした力をバランスよく育てていくには、家庭とスクールの連携も欠かせません。特に言語の面では、日本語と英語の“使い分け”を日常の中で意識できるような環境づくりがカギになります。
中学受験塾との連携について

帰国子女が直面するもうひとつの大きな壁は、「日本式の勉強スタイルへの慣れ」です。
日本の中学受験では、限られた時間で大量の知識を処理し、正解を導き出すスピードと精度が問われます。これは海外で経験してきた、探究型・プロジェクト型の学習スタイルとはかなり異なります。
そのため、受験勉強に特化した中学受験塾との連携は、情報面・学習面ともに非常に有効です。
多くの中学受験塾では、帰国子女向けの特別コースや、個別指導の体制が整っているところもあります。たとえば、日能研やSAPIX、早稲田アカデミーなどの大手塾では、帰国生向けのカリキュラムや模試も用意されており、「どこから手をつけていいかわからない」という不安を一気に解消してくれる存在になり得ます。
また、塾の先生は出題傾向や学校ごとの評価軸を熟知しているため、限られた時間で効率よく準備を進める上でも、強い味方になってくれるでしょう。
大切なのは、「家庭と塾が同じ目線でお子さんを支える」姿勢です。定期的に塾の面談を受けたり、模試の結果を親子で振り返る時間をとることで、塾が単なる“任せっぱなし”ではなく、“一緒に考える存在”になります。
特に日本の受験システムに慣れていないご家庭にとって、塾はナビゲーターのような存在。早めに塾を訪れて、雰囲気や対応を確認しておくと、受験期の安心感がぐっと増します。
帰国子女の中学受験は、制度を知ることと子ども自身を見ることの両立が必要です。
帰国生入試という制度面の特徴を正しく理解しつつ、お子さんのこれまでの経験や性格、得意なこと、苦手なこととじっくり向き合うことで、「どこがいい学校か」ではなく「どこがこの子に合っているか」という視点が見えてきます。
親御さんにとっても、慣れない日本の教育制度や文化に戸惑うこともあるかもしれません。でも、情報を知ることで不安は軽くなり、選択肢も広がります。
受験はゴールではなく、これからの学びの入り口。焦らず、でも一歩ずつ。お子さんの歩調に合わせて、丁寧に進んでいける受験準備を応援しています。