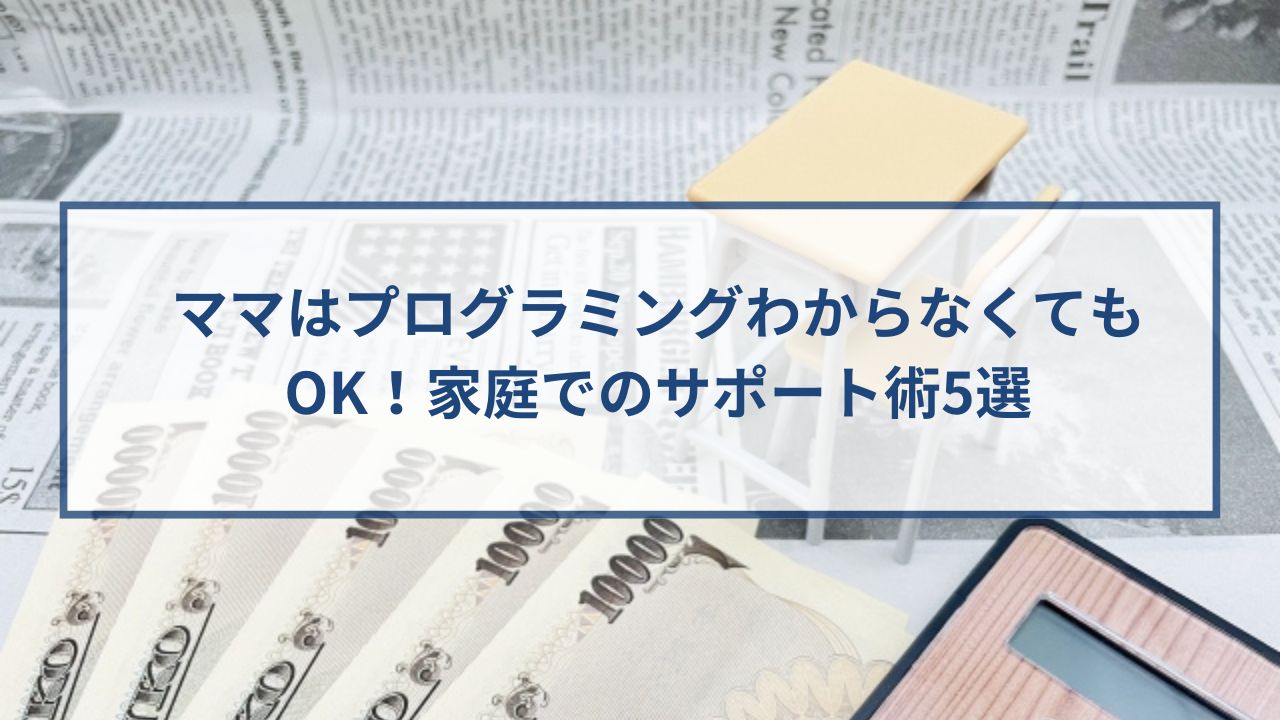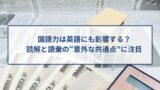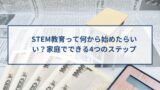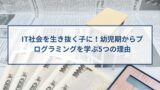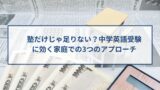「子どもが、プログラミングに興味あるみたい。でも、親の私は全然わからなくて、、」
そんな親御さんの声、最近よく聞くようになりました。
ただ、今のプログラミング教育は、“親が先生になる”必要なんてまったくありません。
むしろ、ママが「わからないけど一緒に楽しもう」と寄り添うことの方が、ずっと価値があるんです。
この記事では、「プログラミングって難しそう」と思っているママにこそ読んでほしい、家庭でできる5つのサポート術をお伝えします。
教育観の変化や具体的な実践例もまじえながら、ゆっくり読んでみてくださいね。
そもそも幼児にプログラミング教育は意味があるの?

そもそも、「幼児にプログラミング教育って早くない?」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、いま話題になっている幼児期のプログラミング教育は、いわゆる“パソコンでコードを書く”ようなものとはまったく違います。
子ども向けのプログラミング教育で重視されているのは、
- 順序立てて考える力(論理的思考)
- 試行錯誤する力(問題解決力)
- 表現しようとする力(創造力)
といった“思考の土台”を、遊びの中で自然に育てること。
実際に文部科学省も、「プログラミング教育=プログラマーを育てることではない」と明言しており、全ての子どもに必要な“考える力”を育てる基礎教育として位置づけています。
使用する教材も、ブロックを並べてキャラクターを動かすようなビジュアル型が中心で、言語的なハードルもありません。
家庭でできるサポート術5選!

ここでは家庭でできるプログラミング教育のサポート術をご紹介します。
- 難しい内容は知らなくて大丈夫。「なにをしているか」だけ見てあげる
- 「結果」より「考え方」を一緒に話してみる
- 間違えても平気な“安心空間”をつくる
- 子どもの「なんで?」を一緒に面白がる
- 自宅だけじゃなく「ふれる場所」を用意してあげる
それぞれ解説します。
難しい内容は知らなくて大丈夫。「なにをしているか」だけ見てあげる
プログラミングと聞くと、「コード」「関数」「デバッグ」みたいな難しい言葉を想像するかもしれません。
でも、幼児〜小学生低学年向けに使われている教材の多くは、言葉を使わず、ブロックを並べて操作する“ビジュアル型”が基本です。
たとえば、「Scratch Jr.」や「Viscuit(ビスケット)」などの教育アプリは、
「ネコを前に進ませる」
「リンゴが落ちてくるように動かす」
など、直感的に操作できる設計になっています。
だから、ご両親がやることは、「内容を理解すること」ではなく、
「どんな動きを作ってるの?」「わあ、動いたね!」と、子どもが作ったものを“見てあげる”ことです。
難しい内容は知らなくて大丈夫。「なにをしているか」だけ見てあげる
プログラミング教育で大切にされているのは、「正しい答え」ではなく、“どう考えたか”というプロセスです。
たとえば、キャラクターをゴールまで動かすとき、
「なんでこの順番にしたの?」
「途中で止まっちゃったのはどうしてだと思う?」
といった“問いかけ”をしてみるだけで、論理的思考や原因と結果を考える力が育ちます。
実際にある例としては
ある5歳の子が、Scratchで「うさぎがジャンプしてニンジンを取る」ゲームを作っていたとき。
途中でうさぎがジャンプしすぎて画面の外に飛んでいってしまったんですが、
ママが「なんで外に行っちゃったんだろう?」と聞くと、
「ジャンプの回数が多すぎた!」と気づき、ブロックを1つ減らして再挑戦していました。
間違えても平気な“安心空間”をつくる
プログラミングに“正解”はありません。
むしろ、「うまくいかないことをどう修正するか」が最大の学びなんです。
でも子どもって、「失敗した」と感じるとすぐ落ち込んだり、「やーめた」ってなりがちですよね。
だからこそ、家庭で大事なのは、“失敗=成長”だと伝えてあげる空気感です。
例えば、「動かないね」ではなく、「おっ、ちょっと違ったね。どうしようか?」と声をかけるだけでも大丈夫です。
親のその一言で、「失敗しても大丈夫なんだ」と思えるようになります。
子どもの「なんで?」を一緒に面白がる
プログラミング教育の本質って、“探究心”を育てることです。
答えを教えるんじゃなくて、「なんで?」「やってみよう!」を繰り返すことが大切です。
だから、ママ自身が“わからない”ことを恐れずに、
「うーん、ママも知らないなあ。でもちょっと面白そうじゃない?」と一緒に調べたり試したりすることが、最高のサポートになります。
例えば、
「このボタン押したら何が起こるの?」
「同じ動きで色を変えたらどうなるんだろう?」
そんな“わからなさ”を、笑いながら楽しめたら、それだけで子どもの「もっとやってみたい!」が加速していきます。
自宅だけじゃなく「ふれる場所」を用意してあげる
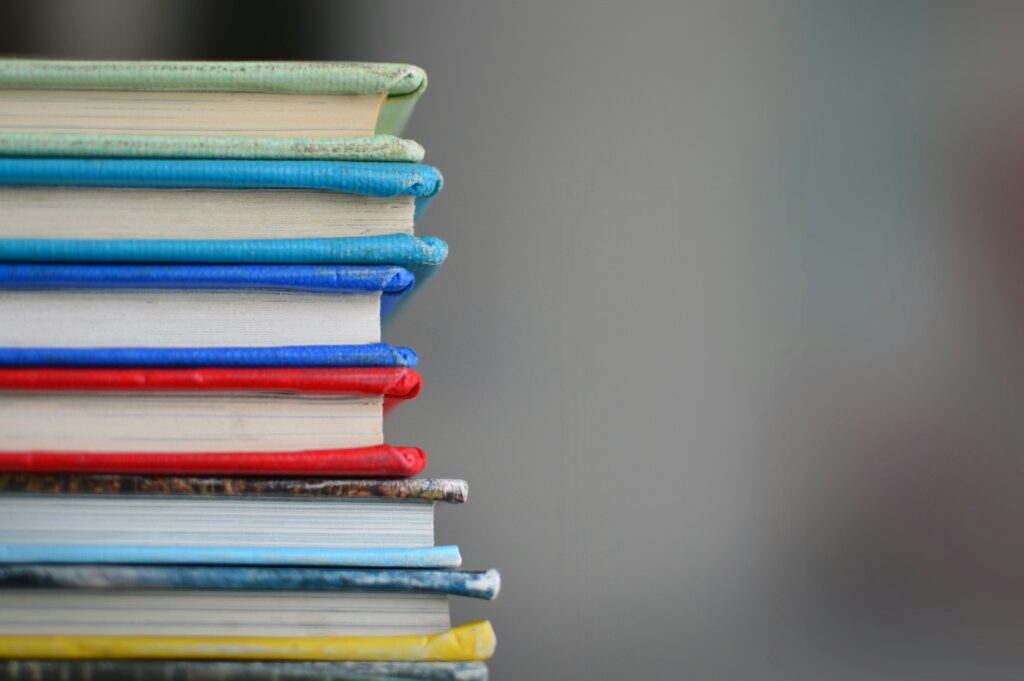
家庭でできることには限界もあります。
だからこそ、“ふれる場所”を少し広げてあげるのも大切です。
たとえば、最近は幼児向けのプログラミング教室がどんどん増えていて、
- カリキュラムが遊び感覚
- 少人数制で安心
- 親のサポートなしでもOK
という教室が多くなってきています。
あるいは、インターナショナルスクールやSTEAM系プリスクールでは、英語+プログラミング+アートなどを組み合わせた教育をしているところもあり、
「遊びながら自然とプログラミングにふれられる環境」が整っているところも。
「プログラミングって、よくわからない」
「教えてあげられないかも」
そんな不安があるママにこそ、知っておいてほしいのは、プログラミングは“家庭で教えるもの”ではないということです。
今の時代に求められているのは、“正しい答え”より“考える力”や“やってみる力”。
だからこそ、ママができるいちばんのサポートは、
「一緒に楽しむ」「失敗しても大丈夫だよって言ってあげる」「ふれる場をつくってあげる」こと。
子どもは、自分で答えを見つけながら、どんどん成長していきます。
ママがわからなくても、その背中をそっと押してあげるだけで、立派な「プログラミング教育の土台」になっていきます。