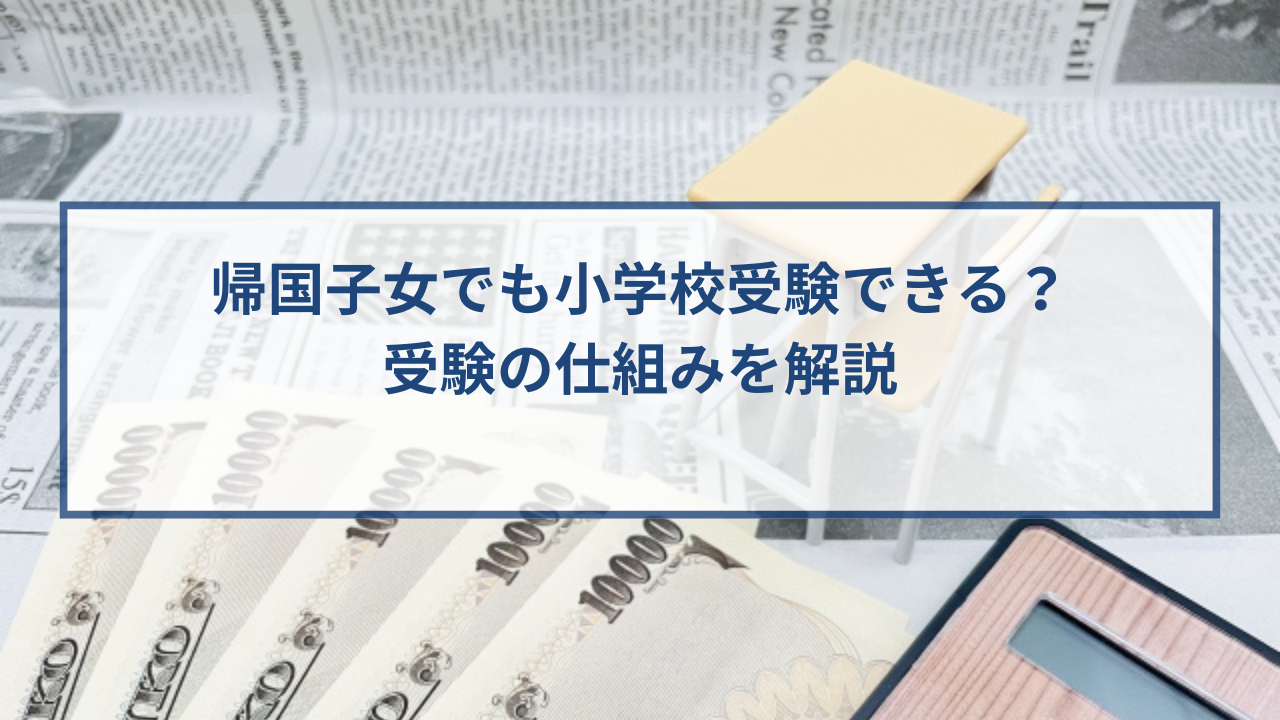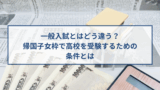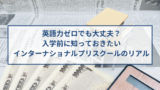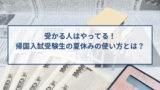「日本の小学校に入りたいけれど、うちの子に合う学校ってどこなんだろう…」
そんな不安を抱えている親御さん、少なくないはずです。特に最近帰国されたばかりのご家庭では、日本の受験事情がわからず戸惑うことも多いのではないでしょうか。
「帰国子女枠はあるけど、うちの子でも大丈夫?」 「日本語が少し遅れているけれど、受験に影響する?」 「海外経験がプラスになるの? それともハンデ?」
帰国直後の子どもは、英語と日本語のバランスだけでなく、文化や生活環境にもギャップを感じやすいものです。そんな中で、小学校受験という大きな選択に向き合うのは、親御さんにとってもプレッシャーが大きいですよね。
この記事では、帰国子女ならではの小学校受験の実態や、受験先としての選択肢、家庭でできるサポートなどについて、安心感をもって理解できるようお届けしていきます。
帰国子女の「小学校受験」ってどうなってるの?

まずお伝えしたいのは、「帰国子女」とひと口に言っても、その経験や背景は十人十色であるということ。アメリカ、シンガポール、ドイツ、オーストラリア…国によって教育スタイルも言語環境も違います。だからこそ、日本の小学校側も「一律の評価」ではなく、その子のバックグラウンドを踏まえた対応をする姿勢が強まっています。
とはいえ、日本の私立や国立小学校での受験には、「帰国子女枠」「国際枠」「一般枠」など、名称こそ違えど似たような制度があります。試験内容や評価ポイントは学校によって異なるものの、共通して「多様な背景を尊重する姿勢」が根づいてきているのが近年の傾向です。
特に、以下のような学校が注目されています:
- 東京都内の私立校(例:聖心女子学院・立教女学院など)
→ 英語対応や帰国子女向けクラスを持ちつつ、カトリック教育など一貫した価値観教育が受けられる点が特徴。面接時には家庭の教育方針や子どもの個性が重視されます。 - インターナショナルスクール系小学校(例:清泉インターナショナル、カナディアン・アカデミーなど)
→ 英語教育が中心。海外のカリキュラムに近いスタイルを継続できるため、日本語に不安がある子どもにとって安心できる環境。英語と日本語のバイリンガル教育が魅力です。 - 国立附属小学校(例:筑波大学附属小学校など)
→ 「帰国枠」という形で優遇されることは少ないですが、家庭での対応力と子どもの柔軟性が試される場所。学力重視の傾向があり、ペーパーテスト対策も必要です。
これらの学校に共通しているのは、「日本でありながら多様性を受け入れる姿勢」を持っていること。ただし、倍率が高く選考も個別なので、事前準備がとても重要になります。
求められる力とは?

帰国子女の小学校受験では、「何ができるか」よりも「どんな経験をしてきたか」「どんな個性を持っているか」が重視される傾向にあります。特に帰国子女枠や国際枠を設けている学校では、子どもの全体像を見てくれる姿勢があります。
とはいえ、やはりベースとなるのは「日本語理解力」です。入試はすべて英語で行われるわけではありませんし、合格後の授業についていくためにも、ある程度の日本語力は必要です。
また、「自己表現力」も重要な要素。これは単なる受け答えのスキルではなく、海外での生活経験や価値観を、面接や作文などでその子らしい言葉で語れるかどうかがポイントになります。
さらに、意外と見落とされがちなのが「集団行動スキル」。日本の小学校では「みんなと一緒に行動する」ことが求められる場面が多くあります。海外の自由な教育スタイルに慣れていると、最初は戸惑うかもしれません。ですが、だからこそ事前に“どういった力が必要なのか”を知っておくだけでも、大きな助けになるのです。
加えて、最近ではICTや英語活動を導入する小学校も増えてきており、帰国子女の強みが活かせるケースもあります。そうした情報をリサーチし、受験先に合わせて準備することも効果的です。
家庭でできる受験サポート

帰国子女の小学校受験において、もっとも大切なのは「海外経験を受験用に矯正しないこと」。
つい、「このままじゃ通用しないかも」と焦って、日本的な型に合わせようとしてしまいがちです。でも実際には、子ども自身の自然な表現や興味、経験がそのまま個性として評価されることも多いんです。
例えば:
- 家での会話で「最近気になったこと」を日本語で話してもらう(日本語力の底上げ)
- 海外で好きだったことをテーマにした絵や作文を書かせてみる(表現力の可視化)
- 面接練習では「答え方」ではなく「感じたことを話す」姿勢を大事に(自己表現の練習)
- 日本の行事や季節行事に親子で積極的に参加する(文化理解と社会性の育成)
- 受験先の学校行事や公開授業に親子で参加し雰囲気に慣れる(学校への理解)
こうした取り組みは、子どもの自信を育み、受験への不安を和らげてくれます。「準備=詰め込み」ではなく、「準備=自分らしさの棚卸し」ととらえて、一歩ずつ取り組んでいくことが大切です。
帰国子女の小学校受験は、決して「日本に適応させるための戦い」ではありません。むしろ、これまで海外で育んできた経験や個性を「どう日本の教育に橋渡しするか」という、前向きな挑戦です。
その中で、親御さんが「うちの子はこういうタイプだから、こういう環境が合うかもしれない」と考える視点がとても大切になってきます。
学校の偏差値や有名度だけでなく、「どんな教育方針があるのか」「どんな子どもたちが集まっているのか」「教師の目はどこを見ているのか」など、柔らかく、広く、深く見ていくことが、子どもにとって本当に意味のある選択になります。
迷っても、わからなくなっても大丈夫。ひとつひとつを丁寧に見ていけば、きっと子どもにぴったりの場所は見つかります。
焦らずに、そして子どもらしさを信じて。一緒に、その一歩を踏み出していきましょう。