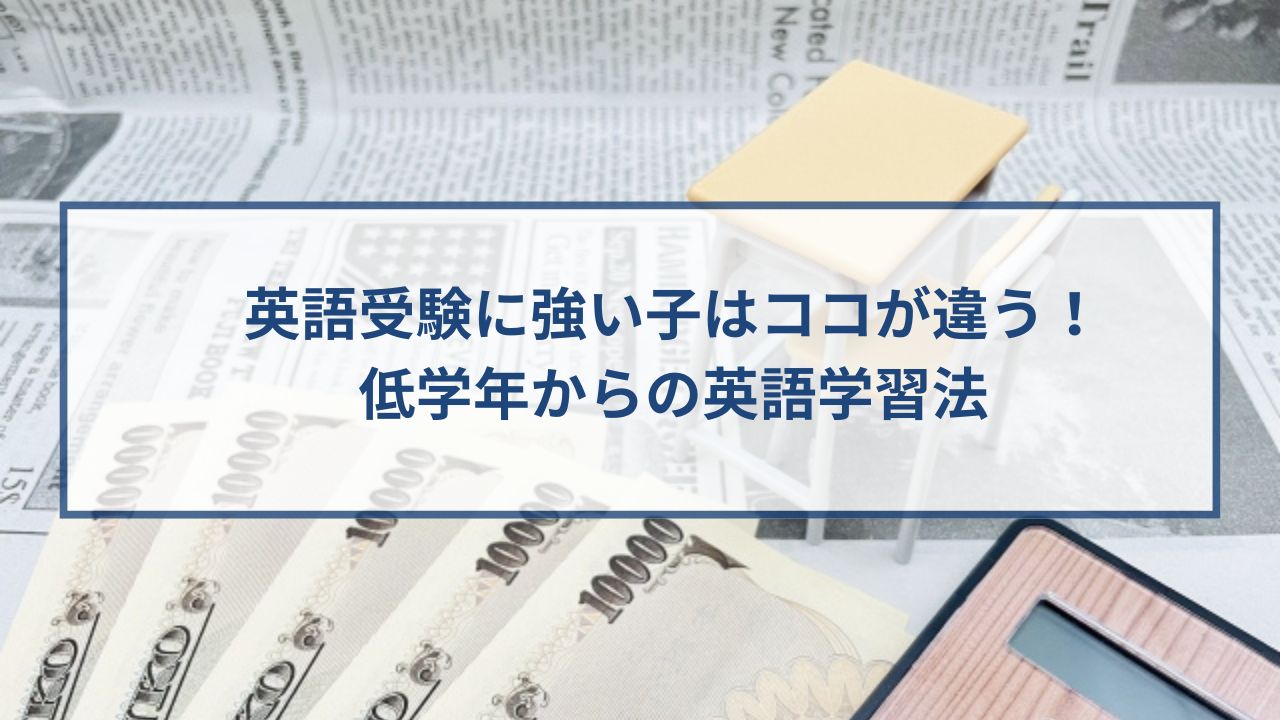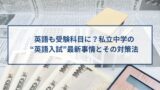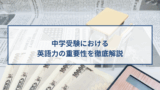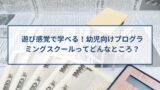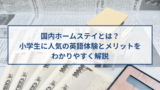「中学受験で英語が出題される学校が増えているらしい」
「でも、まだ小学生のうちから本格的な英語なんて早い気がして…」
そんな戸惑いや不安を感じている親御さんも多いのではないでしょうか。
実際に「英語受験に強い子」は、小さいうちから何か特別なトレーニングを受けているように見えることもあります。
でも、本当に大切なのは“早く始めること”ではありません。
むしろ、低学年のうちに「ことばを考える力」「ことばで伝える力」をどう育てるかが、その後の英語受験の結果を左右します。
この記事では、中学受験で求められる“英語力”の正体、英語に強い子が低学年でやっていること、家庭でできる学習習慣と声かけのコツを、わかりやすくお伝えしていきます。
中学受験における“英語力”の正体とは?

ここ数年で私立中学の中でも、英語を入試科目に取り入れる学校が増えてきました。
たとえば、広尾学園、かえつ有明、三田国際学園、開智中学校などがその代表例です。
でも、これらの学校で求められている“英語力”は、いわゆる単語の暗記や文法知識の量ではありません。
英語で問われているのは、「思考力」や「表現力」
多くの英語入試では以下のような問題が出題されます。
- 英文の読解+内容把握
- 読んだ内容に対する要約や意見文
- 英語で自分の考えを述べる記述問題
つまり、「この英単語の意味は?」というよりも、
“読んで、考えて、伝える”という一連のプロセスにどれだけ対応できるかが評価されるのです。
これは国語と重なる部分も多く、英語でも“ことばの使い方”が問われているというのが実情です。
英語受験に強い子が“低学年でやっていること”

受験英語に強い子の家庭では、低学年のうちから“英語にふれる工夫”が自然に取り入れられています。
ポイントは、知識を詰め込むのではなく、“使う体験”を通してことばを育てていること。
- 多読・多聴で“英語の耳”と“文脈理解”を育てる
- 「言いたいこと」を英語にする習慣
- 親が英語を“教え込まない”関わり方
それぞれ解説します。
多読・多聴で“英語の耳”と“文脈理解”を育てる
英語絵本や英語アニメは、単なるエンタメではなく、言葉のリズムと文の構造を耳で覚える絶好の素材です。
たとえば:
- 毎晩1冊、親子で英語絵本を読む
- アニメを見ながら「この子は何をしてるの?」と日本語で聞く
- 簡単なフレーズ(Good job! / Oh no! / Let’s go!)を親子で真似する
完璧に理解する必要はありません。
大切なのは、“英語の音”と“意味のつながり”をセットで感じる体験を重ねることです。
「言いたいこと」を英語にする習慣
「今日はどんな1日だった?」「何が楽しかった?」と聞いたとき、
その気持ちや体験を、ほんの少し英語で表現してみる練習を取り入れてみましょう。
例)
- 「I played soccer!」
- 「It was fun!」
- 「I ate curry. It was good!」
単語1〜2語だけでも構いません。“言いたいことを英語にしようとする気持ち”こそが、受験での記述力に直結します。
親が英語を“教え込まない”関わり方
実は、英語受験に強い子の親ほど、「自分は英語が得意ではない」と話す方も多いです。
共通しているのは、
- わからないことを一緒に調べる
- 間違いを否定せず、「言おうとしたこと」を受けとめる
- 「失敗してもいいから、英語を楽しむ空気」を大事にしている
“完璧じゃなくてOK”という安心感が、子どもにとっては一番の学びやすい環境になるんです。
低学年のうちに育てたい3つの力とその具体策

中学受験の英語で求められる力を見据えて、低学年から意識しておきたいのが以下の3つです
- 語彙感覚と文の構造にふれる体験
- 自分の意見を“ことばにする”クセ
- 「読む→考える→話す・書く」の循環を意識した声かけ
それぞれ解説します。
語彙感覚と文の構造にふれる体験
英語の意味を日本語に訳すだけでなく、“英語の語順や文の流れ”を体感することが大切です。
- 簡単な英語絵本の“繰り返しフレーズ”を覚える
- 「I like ○○」「This is ○○」などの基本構文を体で覚える
- 単語を並べるのではなく、“まとまり”で英語をとらえる練習をする
これにより、将来の英語読解でも「意味のまとまり=チャンク」で読む力が身につきます。
自分の意見を“ことばにする”クセ
英語で意見を書く問題に対応するには、「自分の気持ちを表現する土台」が必要です。
これは、国語の感想文や読書感想などからも育てることができます。
おすすめは:
- 絵本を読んだあとに「どこが好きだった?」「どう思った?」と聞く
- その感想を日本語で→できれば英語でも一言で言ってみる
例)
- 「I liked the dog because it was kind.」
- 「I didn’t like the ending. It was sad.」
意見を持ち、それを表現する。英語でも国語でも、“自分の考えをことばにする力”は一貫して大切なんです。
「読む→考える→話す・書く」の循環を意識した声かけ
この流れを意識すると、英語も自然に“思考の道具”として機能するようになります。
- 読む(絵本・英語の動画)
→ 内容を考える(どんな話?どう感じた?)
→ 話す・書く(簡単な感想や要約を英語で)
この循環ができている子は、英語受験でも戸惑いません。
“答えを当てる”英語から、“考えを伝える”英語へ。その切り替えを支えるのが、日常の小さな習慣です。
“早く始めたほうがいい”より、“どんな関わり方をするか”

英語受験に強い子は、決して「小さいうちからたくさん詰め込まれた子」ではありません。
むしろ、親御さんが焦らず、「ことばっておもしろいね」と日々の生活に取り入れてきた経験が、学力の土台になっています。
英語が科目として入試に組み込まれる動きは、今後さらに広がっていくでしょう。
でも、それを“焦る材料”にする必要はありません。
最近では、英語に自然にふれられる学習環境を整えたスクールや、中学受験にも対応できるインターナショナル要素を取り入れた私立校も増えています。
“ことばで考えられる子に育てたい”という想いがあれば、英語教育にはきっと前向きな道が開けてきます。