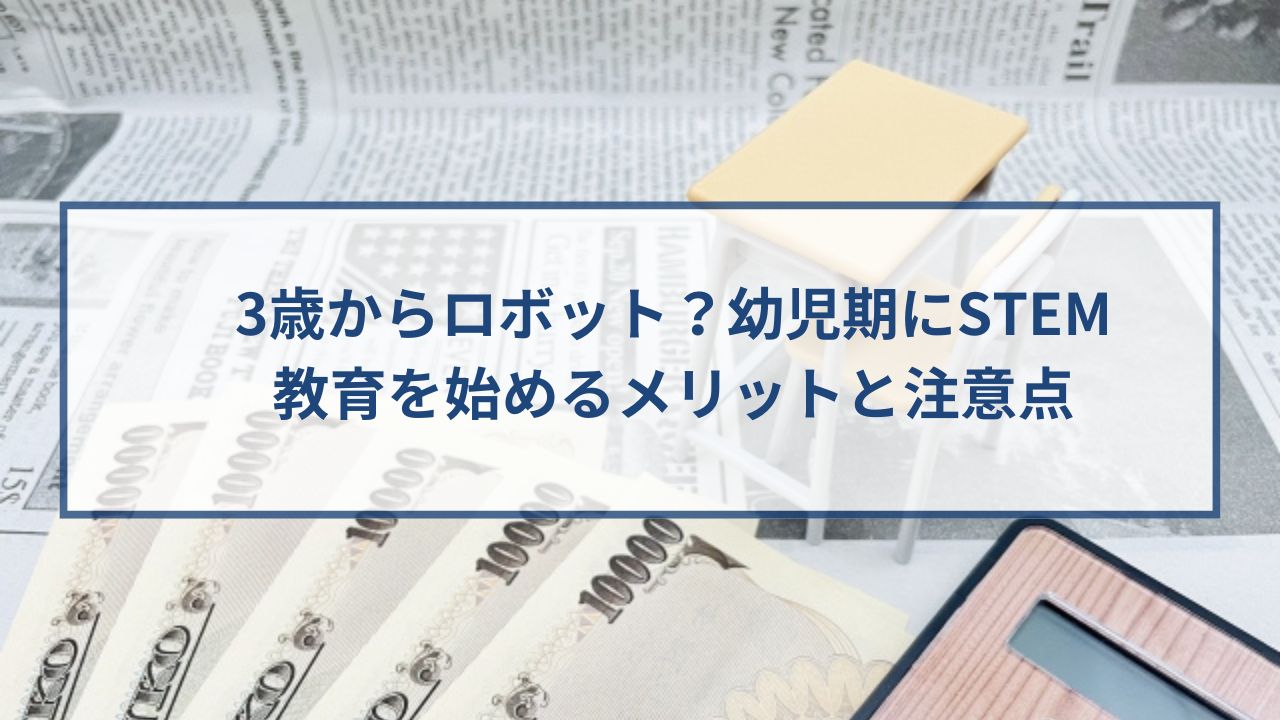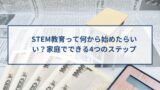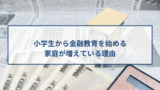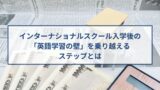最近、「3歳からロボットにふれる」「プログラミング教室に通う未就学児が増えている」など、
STEM教育に関する情報を見かける機会が増えました。
とはいえ、「そんなに小さいうちから本当に必要?」「ついていけるのかな?」と感じるご両親も少なくないはずです。
実際、幼児向けのSTEM教育は、「理系の学習を先取りすること」ではありません。
大切なのは、子どもが「なんで?」「やってみたい!」と感じるきっかけを、遊びを通して育てることです。
この記事では、STEM教育の基礎知識から、メリット、そして始めるうえで気をつけたいポイントまでご紹介します。
そもそもSTEM教育とは?

STEMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の頭文字を取った言葉です。
アメリカを中心に広まり、日本でもここ数年で急速に注目されるようになってきました。
特に、子どもたちが将来生きていく社会は、AI・IoT・ロボティクスなどテクノロジーとの関わりが当たり前になっていきます。
そんな時代に求められるのは、単なる知識の詰め込みではなく、「自分の頭で考えて、問題を解決する力」です。
文部科学省も、非認知能力(粘り強さ・集中力・探究心など)の育成を重視するようになり、
その一環として、幼児教育でもSTEM的な視点が広がっています。
幼児期におけるSTEM教育は、
- 身近な不思議に興味を持つこと
- それを観察・試行錯誤しながら理解すること
- 自分のことばで表現してみること
こうしたプロセスを、遊びの中で自然に育てていくことが目的です。
STEM教育のメリット

ここでは幼少期STEM教育のメリットについて解説します。
- 論理的に考える習慣が身につく
- 自己肯定感と表現力が育つ
論理的に考える習慣が身につく
プログラミング教材やロボット教材を使って、「こうすると、こう動く」「順番が違うと動かない」という体験を積み重ねることで、論理的思考が自然と育っていきます。
例えば、ブロックでキャラクターを動かすアプリでは、
「前に進む→ジャンプ→回る」など、順番に並べて動きを考える必要があります。
この「順序立てて考える力」は、将来の算数や読解、日常生活の段取りにまで応用できる重要なスキルです。
STEMで育った論理的思考力は、教科の枠を超えて活かされます。
たとえば文章を整理する国語の要約、数の意味を理解する算数、観察や記録を要する理科など、すべてに通じる基礎となります。
自己肯定感と表現力が育つ
プログラミングやものづくりを通して、子どもは「自分の力でできた」という感覚を味わうことができます。
うまくいかなくても、何度もやり直して成功したときの達成感は、自己肯定感をぐっと育ててくれます。
こうした“試行錯誤してやり遂げる”体験は、小さなうちに積み重ねておくほど、子どもにとって自然な行動になります。
STEM教育では、動き・音・色・ストーリーなどを自由に組み合わせて表現できる場面が多くあります。
子どもたちは、自分のイメージをかたちにしながら、「どう伝えよう?」と考えるようになります。
これは、表現力や創造力の育成にもつながるポイントです。
STEM教育の注意点

最後に幼児STEM教育で注意すべきことについて解説します。
- やらされ感が出ないようにする
- 年齢に合った教材と環境選び
それぞれ解説します。
やらされ感が出ないようにする
STEM教育は「やらせる」ものではありません。
正解を当てることよりも、「どうしてこうなるんだろう?」と試してみることを楽しめる環境が重要です。
もし「うまくできない」「間違ってばかり」と感じるような体験を重ねてしまうと、
興味が不安や苦手意識に変わってしまう可能性もあるため、最初の“楽しさ”はとても大切です。
「すごいね!」「その発想おもしろいね」といったご家庭や教室のサポートの鍵となる声かけは、
子どもが安心して自由に発想できる空気を作ります。
教室選びでも、「自由に試していいよ」と言ってくれる講師や、のびのびと取り組める雰囲気かどうかをチェックしてみるとよいでしょう。
年齢に合った教材と環境選び
未就学児の場合、文字や数字よりも感覚的に扱える教材が向いています。
たとえば、タッチで操作できる「Viscuit(ビスケット)」や、「ScratchJr」などのビジュアルプログラミングツールは、遊びながら“考える”経験をサポートしてくれます。
また、ブロックやロボット玩具などのアナログ教材でも、「順番」「しくみ」「結果」などに自然と目が向くようになるため、STEM的な入り口として非常に有効です。
最近では、幼児でも参加できるプログラミング教室や、STEM教育に特化したスクールも増えています。
家庭だけで完結せず、外の環境で好奇心を刺激してあげることもひとつの選択肢です。
大切なのは、「続けられること」や「楽しいと思えること」。
まずは体験教室などを通して、子どもに合うスタイルを探してみるのがおすすめです。
STEM教育というと、“理系の先取り学習”のようなイメージを持たれがちですが、
幼児期に必要なのは、知識ではなく「考えるきっかけ」や「やってみようと思える環境」です。
子どもが「おもしろそう」「やってみたい」と感じられること。
そして、それを大人が「いいね!」と応援できること。
その2つが揃えば、立派なSTEMの第一歩になります。
最近では、こうした体験をサポートするスクールも増え、選択肢の幅が広がっています。
もしお子さんに興味の芽が見えたら、気軽にふれられる場所を探してみるのも、ひとつのきっかけになるかもしれません。