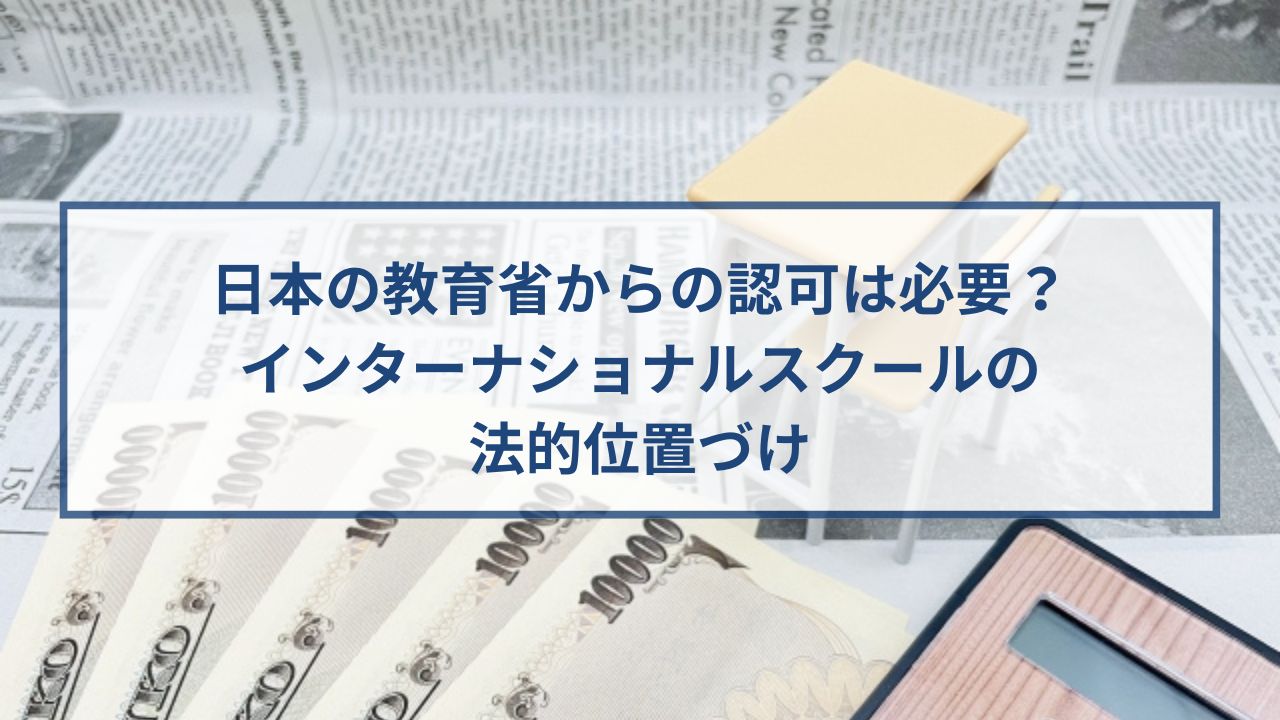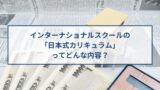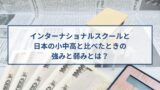インターナショナルスクールを検討する家庭にとって、学費や教育方針と同じくらい大切なのが「法的な位置づけ」です。特に、日本の教育省(文部科学省)から正式に認可を受けているのかどうかは、子どもの学籍や進学に直結するため、多くの親御さんが気になる部分でしょう。
パンフレットには「国際的な教育」「英語環境」「多様な文化」といった魅力的な言葉が並びますが、実際に「この学校は日本の法律上どんな扱いになるのか」は詳しく書かれていないことが多いです。そのため、「無認可だと不利?」「大学進学に影響する?」と不安になる方も少なくありません。
この記事では、インターナショナルスクールが日本の教育制度の中でどのように位置づけられているのかを整理し、認可の有無による違いや、親が押さえておきたいチェックポイントを解説します。
日本の学校制度とインターナショナルスクールの関係とは?

インターナショナルスクールを理解するためには、まず日本の学校制度全体を知る必要があります。なぜなら、インターナショナルスクールの多くはその枠組みに当てはまらないからです。
日本の学校教育法とは
日本では「学校教育法」に基づき、学校が設置・運営されています。小学校・中学校・高等学校・大学など、いわゆる「正規の学校」はこの法律に則り、文部科学省の管轄下に置かれます。ここで学ぶ子どもは、国が認める義務教育や高等教育を受けているとみなされます。
ひとことで言うと、「学校教育法に則った学校=一条校」が、一般的に私たちがイメージする「学校」なのです。
インターナショナルスクールは多くが対象外
しかし、多くのインターナショナルスクールはこの「一条校」には含まれません。法律上は「学校教育法に基づかない教育施設」であり、文部科学省のカリキュラムや管理の対象外です。つまり、日本の制度上は「学校」としては扱われないケースが大半なのです。
このため、親御さんは「じゃあ子どもは義務教育を受けていない扱いになるの?」と心配になりますが、実際には別の枠組みで存在しています。
インターナショナルスクールの3つの位置づけ
インターナショナルスクールは、大きく分けて以下の3つの形で存在しています。
- 一条校(学校教育法第1条に基づく学校)
ごく一部のインターナショナルスクールは正式に「一条校」として認可を受けています。この場合、公立や私立学校と同等の扱いになります。 - 各種学校としての認可校
多くのインターナショナルスクールは、都道府県知事の認可を受け「各種学校」として運営されています。通学定期券や学生ビザの対象となり、公的に一定の認知を受けます。 - 無認可校
法的な枠組みに当てはまらず、認可を受けていない学校です。形式上は「学校」とはみなされませんが、独自の教育方針と国際カリキュラムで評価され、人気を集めています。
認可の有無で何が変わる??

では、インターナショナルスクールが認可されているかどうかで、具体的にどんな違いがあるのでしょうか。
学籍と義務教育の扱い
認可校(特に各種学校以上)の場合、子どもは「学校に在籍している」と公式に認められます。逆に無認可校では、役所や教育委員会から「日本の学校に通っていない」と扱われる可能性があります。このため、地域によっては小・中学校の義務教育を受けていないとみなされるケースがあるのです。
ただし、現実には無認可校でも特例的に在籍が認められる場合や、海外大学進学実績によって事実上評価されることも多くあります。
通学や生活の違い
認可校であれば、通学定期券の学割を使える、学生証が正式に効力を持つなど、生活面でのメリットがあります。無認可校ではこうした制度が使えず、親御さんの経済的負担が増えることも考えられます。
大学進学や資格取得
国内大学を受験する場合、「高等学校卒業資格」が必要です。認可校であればスムーズに取得できますが、無認可校の場合は「高卒認定試験(旧大検)」を受ける必要が出る場合があります。
一方で、多くのインターナショナルスクールは国際バカロレア(IB)、ケンブリッジIGCSE、アメリカンディプロマなどを採用しています。これらは海外大学では高く評価されるため、海外進学を前提とするなら認可の有無は大きな問題にならないケースが多いのです。
無認可でも評価される理由とは??

「認可がない=不利」とは限らないのが、インターナショナルスクールの特徴です。
国際的なカリキュラムの価値
IBやAレベル、SATといった資格は、世界の大学入学に直結します。日本の教育省が認可していなくても、海外大学にとっては重要な評価基準となるため、卒業生が世界中の名門大学に進学することも珍しくありません。
自由度の高い教育環境
無認可だからこそ、日本の教育課程に縛られず、プロジェクト型学習や探究型授業など最新の教育メソッドを柔軟に導入できる学校もあります。子どもの個性や興味を重視した教育を受けられることは、大きなメリットです。
実績の積み上げが信頼を生む
法的な位置づけに関係なく、「この学校からどの大学に進学しているのか」という実績が評価を生みます。実際、無認可でも海外大学への進学率が高く、評判を得ている学校は少なくありません。
親が確認しておきたいチェックポイント4選

法的位置づけが複雑だからこそ、学校を選ぶときにはいくつかの視点を持つことが大切です。
認可の有無を必ず確認する
説明会や公式サイトで「一条校なのか」「各種学校なのか」「無認可なのか」を確認しましょう。学費だけで判断すると後で不安が出てくるため、制度上の扱いを知っておくことは必須です。
進学実績をチェック
認可の有無以上に大切なのは「進学実績」です。海外大学を目指す場合はIBやSATの合格実績、日本大学を視野に入れる場合は高卒認定サポートがあるかを確認する必要があります。
国内進学との両立を考えるかどうか
「海外に進むかまだ分からない」という家庭は、日本語教育や国内進学の情報提供をしてくれる学校かどうかをチェックしておくと安心です。
実際の生活サポート
通学定期や奨学金制度、学割など生活に関わる部分は見落としがちですが、長期的には大きな差につながります。学校訪問時にぜひ質問しておきたいポイントです。
まとめ

インターナショナルスクールの法的位置づけは、日本の教育制度の枠組みでは特殊です。
- 多くは「一条校」ではなく、各種学校または無認可校として存在
- 認可の有無によって、学籍・生活支援・国内大学進学ルートが変わる
- 無認可でも国際カリキュラムや実績により、海外大学進学には十分対応可能
大切なのは「認可の有無=良し悪し」と短絡的に判断しないこと。家庭がどの進路を重視するのかを明確にし、それに合った学校を選ぶことです。
法的位置づけは少し複雑でわかりにくい部分ですが、ここを理解しておくと後から「知らなかった」と後悔するリスクを減らせます。安心して子どもに合った環境を選ぶための基盤として、ぜひ意識して確認しておきましょう。