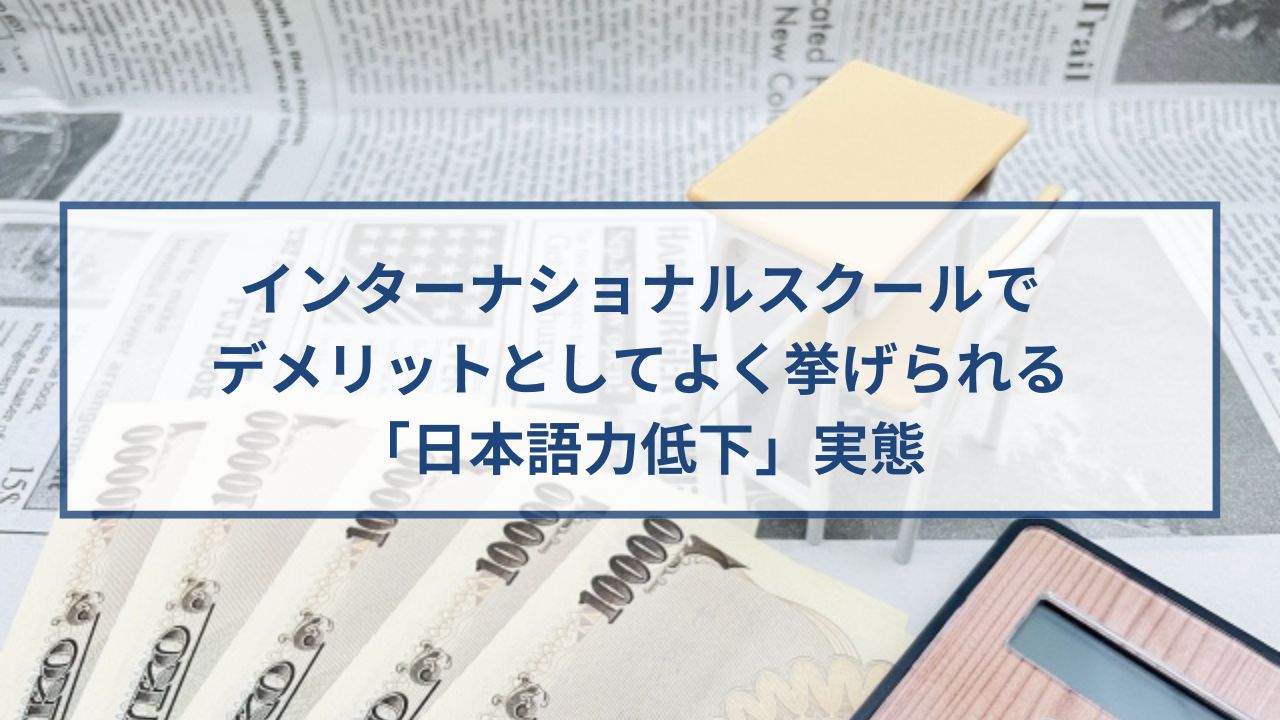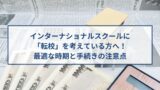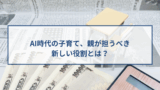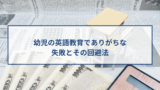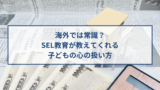インターナショナルスクールに子どもを通わせることを検討している親御さんの多くが、まず思い浮かべるのは「英語力が大きく伸びるだろう」という期待です。授業も会話もすべて英語で行われる環境に身を置けば、自然と耳が慣れ、口から英語が出てくるようになる。それは、従来の日本の学校では得られない貴重なメリットといえるでしょう。
一方で、その裏返しとして「日本語力が弱まってしまうのでは」という心配も少なくありません。特に、日本での生活や進学を考える上で日本語は避けて通れない基盤です。英語力が伸びるのは魅力的でも、母語である日本語が十分に育たないとなれば、子どもの学びや将来にどう影響するのかと不安になるのは当然です。
この記事では、インターナショナルスクールに通った場合に実際に起こりやすい日本語力低下の実態を、原因や背景とあわせて丁寧に解説します。また、具体的にどのような影響があるのか、そして親がどんなサポートをすることでリスクを減らせるのかについても詳しく触れていきます。
日本語力低下は本当にあるの??

まずは「実際に日本語力は落ちるのか?」という根本的な疑問に向き合ってみましょう。インターナショナルスクールに通う子どもたちの間では、確かに共通して見られる傾向が存在します。
実際に見られる低下の傾向
日本語力の低下といっても、その程度は子どもや環境によって異なります。しかしよく報告されるのが、漢字の読み書き、語彙力、文章表現の弱さです。小学校低学年の段階では日常会話レベルに大きな違いは見られなくても、高学年になると「作文が短く単純になりがち」「教科書的な漢字が書けない」といった差が出てくることがあります。
さらに、言葉のニュアンスや敬語の使い分けといった「高度な日本語表現」が育ちにくいのも特徴です。例えば親戚と話すときに「丁寧な日本語が出てこない」「語彙が限られていて説明がまわりくどくなる」といった場面は、親御さんが特に気づきやすい部分です。
日本語力低下が目立つ具体的な場面
- 学校外で日本の友達と遊んでいるとき、会話のテンポについていけず簡単な言葉ばかりになる
- 日本語の本を読むのに時間がかかり、内容を深く理解できない
- 作文や日記を書くとき、英語の語順や発想が混ざってしまい不自然な表現になる
これらは多くの家庭で実際に起こり得る光景です。「話せるけれど深く使えない日本語」が子どもに定着してしまうと、後々の学びにも響きやすくなります。
なぜ日本語力が低下するの??

次に、その原因を整理してみましょう。インターナショナルスクールの教育方針や生活環境が、日本語の発達にどのように影響しているのかを理解することが重要です。
英語が生活の中心になる
最大の理由は、学校生活のほぼすべてが英語で行われる点にあります。授業はもちろん、友達との会話、課題提出、イベントでの発表まで英語が基本です。子どもにとって「考える」「話す」「書く」のすべてが英語中心になり、日本語を使う場面が家庭に限られてしまいます。結果として、母語のアウトプット機会が圧倒的に不足してしまうのです。
国語教育の不足
多くのインターナショナルスクールでは日本語の授業が用意されていますが、その時間数は限られています。日本の学校で毎日国語に触れるのに比べ、週数時間の授業だけでは十分な力を伸ばすのは難しいのが現状です。特に漢字の習得や文章構成力は、継続的で体系的な学習が不可欠ですが、その点で差が生まれやすくなります。
家庭での言語環境
家庭で日本語をどれだけ使うかも大きな影響を与えます。親が積極的に日本語を話したり、本や新聞を読ませる環境を整えている家庭では低下が緩やかですが、家庭でも英語が中心になる場合は日本語力が一層伸びにくくなります。家庭の役割が、日本語維持において非常に重要であることがわかります。
日本語力低下が与える影響

では、日本語力が十分に育たなかった場合、将来的にどのような影響が出るのでしょうか。
日本の大学進学への不利
日本の大学入試は依然として日本語での学力試験が中心です。帰国生入試やAO入試を利用できる場合もありますが、一般入試を受けるとなると国語力不足が大きな壁になります。小論文の課題に苦戦する、読解問題で時間が足りないといったケースは珍しくありません。
就職活動での課題
社会人になれば、ビジネス文書や敬語を使ったやり取りが求められます。日本語力が不十分だと、エントリーシート作成や面接で自分をうまく表現できないことがあります。外資系や海外で働く場合は強みが活かせますが、日本企業を志望する場合には課題が残ります。
アイデンティティへの影響
母語である日本語に苦手意識を持つことは、子どもの自己肯定感やアイデンティティ形成に影響することもあります。「自分は日本人なのに日本語が苦手」という感覚は、思春期以降の自己認識に影響することがあるのです。これは家庭でのサポートや成功体験の積み重ねで緩和できますが、早めの意識が大切になります。
日本語力を補うための工夫

しかし、日本語力低下は決して避けられないものではありません。家庭で意識的に取り組むことで、英語と日本語をバランスよく育てることは可能です。
家庭での日本語読書
親子で一緒に日本語の本を読む習慣を作ることは効果的です。絵本からスタートして、徐々に物語や歴史、科学の本などへ広げていくと自然に語彙が増えていきます。読み終えた後に内容を話し合うことで、理解力と表現力も養えます。
書く習慣を持たせる
日記や感想文、手紙など、自由に日本語で書く機会を増やすことも大切です。内容に完璧さを求めるのではなく、「自分の考えを日本語で表す」ことを繰り返すことで表現の幅が広がります。
日本の教育資源を活用する
日本語を補うために、日本の通信教材や国語塾を利用する家庭もあります。特に漢字や作文の基礎は、専門的にサポートしてもらうと安定して力を伸ばせます。インターナショナルスクールと併用している家庭も多く、実績として効果が確認されています。
インターナショナルスクールと日本語教育の両立

大切なのは「英語か日本語か」の二者択一ではなく、両立の意識です。インターナショナルスクールに通うこと自体が日本語力低下を必然とするわけではなく、家庭や周囲の関わり方によって結果は大きく変わります。
英語環境で育つことは子どもにとって大きな資産です。しかし同時に、日本語力をどう維持し伸ばすかを考えることが、より豊かな未来につながります。親が意識的に日本語環境を整え、子どもの努力をサポートすれば、英語と日本語の両方を高いレベルで身につけることも夢ではありません。
インターナショナルスクールにおける日本語力低下の実態は確かに存在します。しかし、それは決して克服できないものではありません。
- 日本語力の低下は漢字・作文・語彙力に表れやすい
- 原因は英語漬けの生活、国語教育の不足、家庭での日本語使用の減少
- 影響は進学、就職、アイデンティティ形成に及ぶ
- 読書や作文、教材活用で十分に補える
インターナショナルスクールは子どもに国際的な視野を広げる場であり、同時に日本語教育を家庭で意識的に支えることができれば、両方の言語を自在に使える大きな強みを手に入れることができます。親御さんにとって大切なのは「どちらを優先するか」ではなく、「どう両立させるか」を考えることなのです。