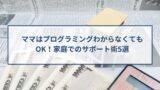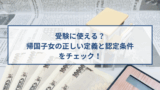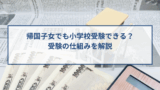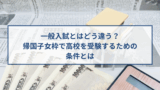帰国生入試を目指す高校生にとって、夏休みは単なる長期休暇ではありません。むしろ、ほかの時期では得られないまとまった時間がとれる貴重な期間。そしてこの時間の使い方が、秋以降の受験の手応えを大きく左右していきます。
「夏こそ本気を出そう!」と意気込んでスケジュールを立ててみたものの、何から始めればいいのかわからなかったり、モチベーションの波に左右されたり。そんな不安や焦りを感じている人もいるのではないでしょうか?
帰国入試は、一般入試と比べて求められる力や評価のされ方が少し違う部分があります。だからこそ、帰国入試ならではの「夏の過ごし方」を知っておくことが大切です。
焦らなくて大丈夫。でも、何もしないのはもったいない。そんな気持ちに寄り添いながら、帰国入試大学受験生の夏のヒントをお届けします。
社会の変化と、帰国入試で求められる力

ここ数年で、大学入試を取り巻く環境は大きく変化しています。とくに帰国生入試においては、語学力や学力に加えて、表現力・主体性・多文化理解などその人自身の中身がより重視される傾向にあります。
背景にあるのは、日本社会全体のグローバル人材へのニーズの高まりです。
- 高校生のうちからの探究学習やIB教育の普及
- 国内大学でもAO・総合型選抜が重視される流れ
- 「英語ができる」だけでは足りないという価値観の変化
こうした流れの中で、帰国生入試では「帰国経験の中で何を感じ、どう考え、今後につなげたいと思っているか」といった、自分の軸を持った思考が求められます。
たとえば、上智大学や早稲田大学、ICU(国際基督教大学)などの帰国生入試では、面接や志望理由書で「個人としての成長」や「国際社会への関心」がどれだけリアルに語れるかがカギになります。また、STEM分野に力を入れている東京理科大学や慶應義塾大学SFCなどでは、「探究心」「課題解決能力」を問う傾向が強くなっています。
つまり、英語のスコアやGPAといった数字だけでなく、「あなたらしさ」「あなたの視点」が強く求められるということです。その準備は、教科書を開くだけではできません。むしろ、日々の経験の積み重ねや、考えを深める習慣の中にヒントがあります。
だからこそ、英語の勉強はもちろん、「自分のことを言葉にする力」や「学びを自分ごとにする視点」も、夏のうちから少しずつ育てておく必要があるのです。
一般入試と違って、受験対策が「過去問を解くこと」だけに限らないのが帰国入試の特徴。逆にいえば、夏休みをどう過ごすかで、他の受験生と大きな差がつけられるチャンスともいえます。
帰国生入試の夏に整えたい3つのこと

では、夏の間にどんな準備をしておけば、帰国入試に向けて安心できる状態になれるのでしょうか?ここでは、家庭の中で意識できるポイントを3つ紹介します。
- 自分の経験を言語化する習慣をつくる
- 英語と日本語の行き来をスムーズにする
- スケジュールを自分で考えて立てる体験を入れる
自分の経験を言語化する習慣をつくる
帰国生入試では、面接や志望理由書などを通じて「自分の体験をどう捉えているか」が問われます。たとえば、「海外での学校生活で驚いたこと」「文化の違いで悩んだこと」「その経験から学んだこと」などを、少しずつ振り返ってみましょう。
とはいえ、いきなりエッセイを書くのはハードルが高いですよね。おすすめは、毎日のミニ日記や親子での会話の中で、自分の考えを言葉にしていく練習をすること。
たとえば、 「今日読んだニュースについてどう思った?」 「中学のときのあの経験って、今振り返るとどう感じる?」 といった問いかけを日常に入れていくと、自分の言葉で考える習慣が自然と身についていきます。
英語と日本語の行き来をスムーズにする
帰国生の多くが感じる壁のひとつが、「英語では話せるけど、日本語で説明しようとすると難しい」というものです。面接や志望理由書では、日本語での表現も求められることが多いため、言語の切り替え力を高めておくことはとても重要です。
夏の間にできることとしては、英語で読んだ記事や本の内容を日本語で要約してみる、日本語の小論文を書いたあとに英語でまとめ直してみるなど、英語と日本語を行き来するトレーニングを意識して取り入れてみましょう。
親御さんと一緒にニュースを見て、それぞれの言語で感想を言い合うのも立派な練習になります。難しい話題じゃなくてもOK。「このCMどう思った?」くらいのラフなテーマでも、十分なアウトプットの場になります。
スケジュールを自分で考えて立てる体験を入れる
夏休みは自由度が高いぶん、「何をすればいいかわからず時間だけが過ぎてしまう」ということもあります。
ここで大事なのが、やるべきことを一緒に考えながら、本人が自分のスケジュールを主体的に立てる経験を積むことです。たとえば、「午前は志望理由の下書き、午後は日本語面接の練習、そのあと1時間だけNetflixでリスニング」というように、学習と休憩のバランスを自分で設計する力を育てていくのです。
すべて完璧にこなす必要はありませんが、「こうやって組み立てたらうまくいった」「これはうまくいかなかったけど、次はこうしてみよう」という試行錯誤が、受験本番の計画力にもつながります。
この自分で考えて動く力は、まさに帰国生入試で評価されるポイントのひとつです。夏のうちから少しずつ体験していくことで、学力以外の部分でも強みをつくっていけるはずです。
外部のサポートをどう活かす?

帰国入試に向けては、家庭だけでできる準備に限界があることも事実です。特に日本語での面接対策や志望理由書の添削、出願書類のチェックなどは、専門的な視点からのアドバイスがあると格段に精度が上がります。
たとえば、帰国子女専門の塾や、オンラインでの小論文添削・模擬面接を受けられるスクールを利用することは、今や一般的な選択肢です。Z会やベネッセなどの大手でも帰国生向けの対策講座を展開しており、個別指導や模試を活用している受験生も多く見られます。
また、学校の先生に相談しながら、国内外の大学に精通した進路指導教員と一緒に方針を練るのもおすすめ。特にアメリカ式やIB式のインターナショナルスクールに通っていた場合、日本の帰国生入試の文化とのギャップがあることもあるため、専門家と連携して準備を進めることが安心につながります。
とはいえ、外部の環境を活かすうえで大事なのは、「任せきりにしないこと」。あくまで自分の意志を軸にして、「どう活用するか」を考える視点を持つことが、学びの質を高めてくれます。
帰国生入試は、ただ知識を詰め込むだけでは通用しない入試です。求められるのは、その人にしか語れない経験やその人らしい視点を言葉にする力。
そしてそれは、一朝一夕で身につくものではありません。だからこそ、夏の時間をどう過ごすかが、大きな意味を持ってくるのです。
毎日を完璧にこなす必要はありません。でも、「今日はこんなことを考えた」「こんなふうに工夫してみた」という小さな積み重ねが、秋以降の面接や出願書類の説得力になっていきます。
この夏が、あなたにとって受験の準備を超えた、人生を語る準備になることを願っています。