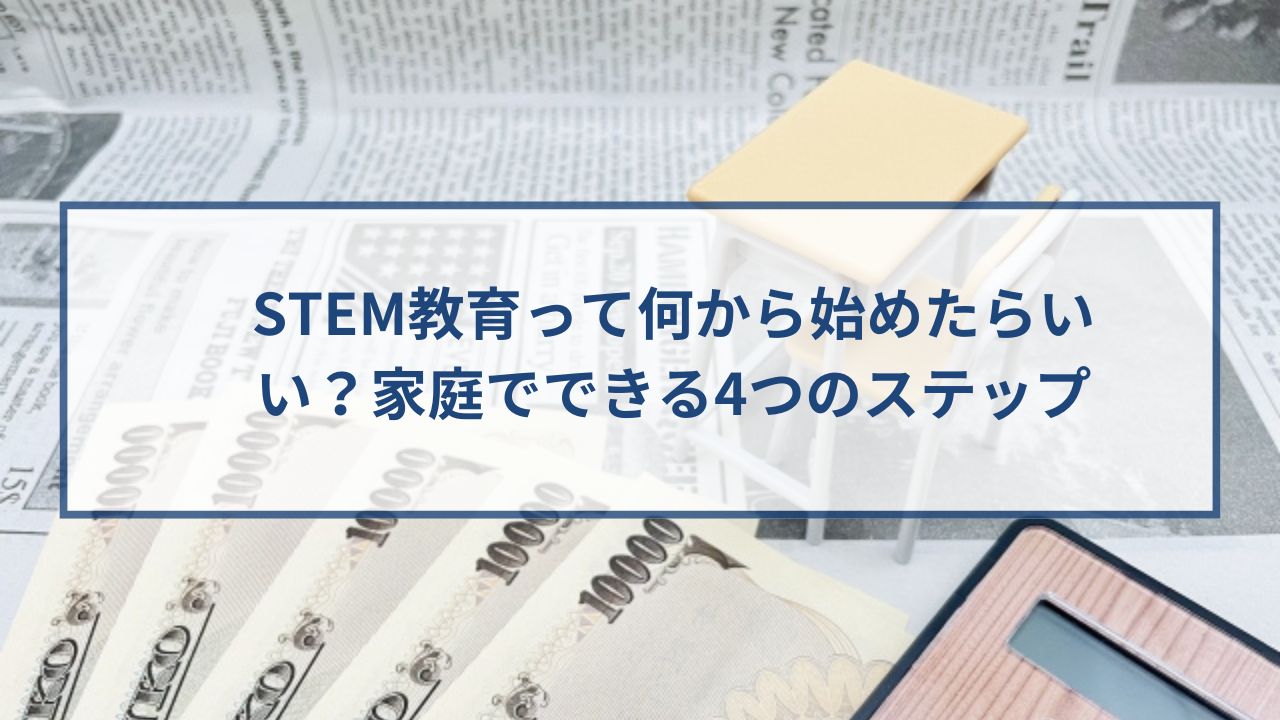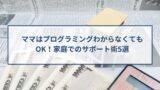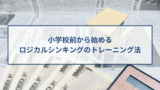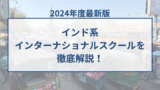最近「STEM教育」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
でも、「なんだか難しそう」「専門的な知識が必要そう」と感じている親御さんも多いのではないでしょうか。
実は、STEM教育の入り口はとても身近なところにあります。
特別な道具や教材がなくても、子どもの「なんで?」「やってみたい!」に寄り添うことから、立派なSTEM教育は始まっているんです。
この記事では、そんなSTEM教育を「家庭で気軽に始めるための4つのステップ」をご紹介します。
無理なく、でもしっかりと“考える力”を育てていくヒントになれば幸いです。
そもそもSTEM教育とは?

STEMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の頭文字を取った言葉です。
アメリカを中心に広まり、日本でもここ数年で急速に注目されるようになってきました。
特に、子どもたちが将来生きていく社会は、AI・IoT・ロボティクスなどテクノロジーとの関わりが当たり前になっていきます。
そんな時代に求められるのは、単なる知識の詰め込みではなく、「自分の頭で考えて、問題を解決する力」です。
文部科学省も、非認知能力(粘り強さ・集中力・探究心など)の育成を重視するようになり、
その一環として、幼児教育でもSTEM的な視点が広がっています。
幼児期におけるSTEM教育は、
- 身近な不思議に興味を持つこと
- それを観察・試行錯誤しながら理解すること
- 自分のことばで表現してみること
こうしたプロセスを、遊びの中で自然に育てていくことが目的です。
家庭でできるSTEM教育4つのステップ

ここでは家庭でできる4つのSTEM教育について解説します。
- 好奇心をくすぐる“問いかけ”から始める
- おうちでできる小さな実験を楽しむ
- プログラミング的思考にふれてみる
- 探究を広げる環境を用意してみる
それぞれ解説します。
好奇心をくすぐる“問いかけ”から始める
STEM教育は、何かを“教える”ところから始めなくても大丈夫です。
むしろ、子ども自身が「これなに?」「どうしてこうなるの?」と疑問を持つことこそが、最初の入り口になります。
例えば、
- 「なんで雲は白いんだろうね?」
- 「お湯を入れると色が変わるの、なんでだと思う?」
- 「冷蔵庫の中の水は、ずっと冷たいのかな?」
こんなふうに、日常の中でふとした“なんで?”を拾ってあげることが、立派なSTEMの第一歩になります。
親のスタンスは「一緒に考える」というスタンスを取るべきです。答えを知っていなくても大丈夫です。
「ママも知らないなあ。一緒に考えてみようか?」という姿勢が、子どもにとって“考えることは楽しい”という印象につながっていきます。
おうちでできる小さな実験を楽しむ
子どもたちにとって、体を使った体験は“学びの宝庫”です。
特に、結果が目に見えて変化する「かんたん実験」は、好奇心を引き出すのにぴったり。
例えば、
- 色水にスポイトで混色してみる
- 氷に塩をかけて溶ける様子を観察する
- 水に浮くもの・沈むものを比べてみる
- 静電気をつかってティッシュを動かす
こうした実験は、“仮説→観察→結果→発見”という思考の流れを自然に体験できるのが魅力です。
大がかりな道具は必要ありません。
わざわざ特別なキットを買わなくても、
キッチンにある道具や、100円ショップで揃うもので十分始められます。
「面白かったね」で終わらせず、
「どうしてこうなったんだろうね?」と声をかけるだけでも、ぐっとSTEMらしい学びに近づきます。
プログラミング的思考にふれてみる
プログラミングというと難しく聞こえますが、幼児向けの教材は「遊びながら考える」ことに特化しています。
たとえば「ScratchJr」や「Viscuit」は、文字が読めなくても使える設計で、ブロックを並べるだけでキャラクターを動かすことができます。
こうした教材を使うことで、
- 「何をどの順番でやるか」
- 「動かなかった原因はどこか」
- 「直すにはどうしたらいいか」
といったプログラミング的な思考力が自然と身についていきます。
よくある不安として、「自分がプログラミングを知らないから、教えられない」という声もありますが、
実際のところ、“一緒に試してみる”だけで十分です。
親が「できるか」よりも、「楽しそうにやってるな」「うまくいったね」と見守ってくれる存在であることの方が、子どもの成長には大きな影響を与えます。
探究を広げる環境を用意してみる

子どもの「もっと知りたい!」という気持ちが芽生えたら、それを広げていくチャンスです。
たとえば…
- 図鑑や科学絵本を読み聞かせてみる
- 動物や植物をテーマにした探究系YouTubeを一緒に観る
- 科学館やプラネタリウムに出かけてみる
そういった「日常から少しだけ広げた学び」の中で、子どもは自分の中にある興味を深めていきます。
もし「もっとやってみたい」「もっとふれてほしい」と感じたときは、
プログラミングや探究学習を取り入れている教室やスクールなど、“環境”を外に求めることも選択肢のひとつです。
最近では、遊び感覚でSTEMにふれられる教室も増えており、
家庭での好奇心をさらに広げていくステージとして活用されています。
STEM教育は、「専門知識が必要な難しい学び」ではありません。
むしろ、“なんで?”と感じたことに向き合ってみること、
そして「一緒にやってみよう」と寄り添ってくれる環境があれば、そこから自然と始められるものなんです。
そして今では、そんな興味や好奇心をさらに育ててくれる環境として、
プログラミング教室やSTEAM型スクールを選ぶご家庭も少しずつ増えてきました。
ご家庭の中でできること、外の環境をうまく活用すること。
どちらかひとつに決めなくても、子どもの興味に合わせて選んでいけば、それが一番のSTEM教育になります。