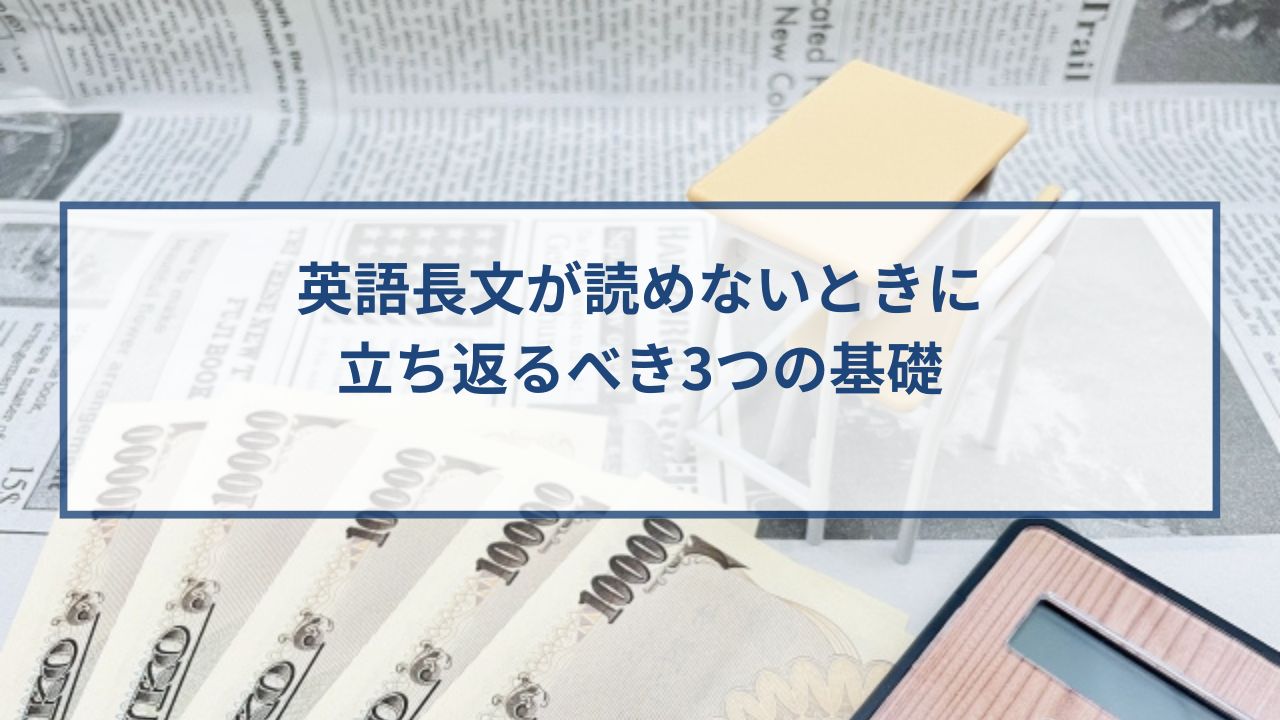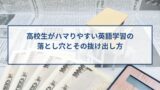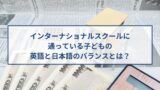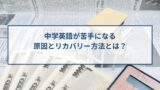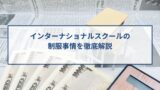「設問に時間を取られて本文理解がスカスカになる」「結局どこから直せばいいのか分からない」
英語長文が読めないと感じるとき、必要なのは気合いより順番。闇雲に問題数を増やすより、読みを支える土台を3つだけ整える方が回復が早いです。
ここでは、前から処理する語順の感覚、コアの意味でつかむ語彙、音から支える読み筋という三本柱にしぼって、家でも再現できる練習と戻し方をまとめました。テクニックではなく、明日から淡々と回せる基礎に降ろしていきます。
基礎1:英語は前からかたまりで読む

長文でつまずく多くの原因は、実は単語力不足ではありません。日本語の語順に引きずられて後ろから意味を拾おうとする返り読みが、読む体力を奪っていることが多いです。
英語は主語→動詞→目的語→修飾の順に情報が流れます。だから、目の動きも前から。ここを取り戻すだけで、スピードと理解の両方が上がります。まずは文を小さなかたまり(チャンク)に分け、返り読みを封じる型を体に入れましょう。最初はゆっくりでいいので、必ず前へ進むことを守ります。
かたまりの見つけ方
文の骨格は主語(S)と動詞(V)。ここが見えれば8割勝ちです。最初の名詞か名詞句を主語に置き、動詞を探したら、その後ろに目的語(O)や補語がいるかを確認。前置詞のかたまり(in the morning / at school など)や関係代名詞の節は尾っぽとして後回し。まず骨をつかまえる。これだけで、文の重心がブレません。
スラッシュリーディングで返り読みを封じる
1文を短いチャンクに切って前から声に出します。
例:The new library / that opened last month / offers students / a quiet place / to study after classes.
返さず前へ。意味があいまいでも止まらない。切る位置に正解はありませんが、名詞句・動詞・前置詞句・to不定詞・関係節で切るのが基本。まずは教科書レベルの英文で1日10文、1週間続けると目の運びが変わります。
段落は最初と最後を丁寧に、中は滑らせる
段落の主張はトピックセンテンス(多くは最初)とシグナル(結論や転換)に現れます。ここを丁寧に、真ん中はチャンクで滑らせながら何の話かのラベルだけ貼る。読む目的は100%の和訳ではなく設問に答えるための理解。前から情報を受け取り続ける姿勢が、最後まで読む体力を作ります。
基礎2:語彙はコアの意味+くっつき方で覚える

長文が読めないとき、単語帳を増やすより「覚え方」を変える方が効きます。英単語は核となるイメージ(コア)と一緒に使われやすい言い回し(コロケーション)でつかむと、本文での当たりがよくなります。
さらに品詞を意識できると、未知語でも文の役割で推測しやすくなります。ここでは、ただの訳語暗記を使える語彙に変える三つの視点を置きます。
コアでつかむ
例えばissueは問題だけでなく発行する・提示するの意味もありますが、コアは「外へ出す」。そこから発行物、論点(外へ出された話題)に広がる。
setは「置く・定める」、subjectは「従属させる/題材」など、中心のイメージを一つ決めると、文脈でのブレが減ります。長文はこのにおいで読むのが近道です。
コロケーション
make a decision / play a role / raise a question のような“相性の良い並び”は、辞書で太字や例文の最初に出てきます。長文に出たときに迷わないよう、覚えると決めた単語に1ペアだけ相棒をつけてノートに残す。単語の孤立をなくすほど、読むときにスルッと意味が落ちます。
品詞で読む
未知語でも、最後が -tion / -ment なら名詞、-able / -ous なら形容詞、と役割が推測できます。文の骨(SVO)に直接絡むのは主に名詞と動詞。ここが分かれば、修飾の形容詞・副詞は後回しでも読みが進む。語形変化(decide→decision、possible→possibility など)を1対で覚えると、設問の品詞指定にも強くなります。
基礎3:音で支える読解

黙読だけでは、目が勝手に返り読みを始めます。音読とシャドーイングは、脳に“英語は前から流れる音”だと教え直す作業。
発音の完璧さは不要で、狙いは語順の流れとチャンクの切れ目。1日10分でも、音を通すと長文に触れる抵抗が下がり、読むときの引っかかりが目に見えて減ります。テキストは教科書本文や標準的な長文で十分。やり方を固定して淡々と回しましょう。
音読3セット法
下見(語句確認)1分、追い読み(親or音声の後に同じ文を被せる)2分、通し音読(段落を前から)2分を1セット。息継ぎの位置=チャンクの位置だと思って、止まらず進む。噛んだら文頭に戻らず、その文の頭だけやり直して次へ。“戻らない”が最重要です。
シャドーイング
最初から等速で無理をすると崩れます。スマホの再生速度を落として、1文遅れのシャドーから、慣れたら等速へ。聞こえなかった箇所は捨てて、次のかたまりに乗る。意味が薄くても、語順の波に乗れたかを自分に問い続けると、黙読に戻ったときの目の運びがスムーズになります。
サイトトランスレーション
英語のチャンクごとに、その場で簡単な日本語を前から当てていく練習。The report / suggests / that many teenagers / are changing their habits. を「その報告書は/示している/多くの10代が/習慣を変えつつあると」のように。日本語でも前から処理するクセをつけると、返り読みの誘惑が薄れます。
読解を点に変える手順:設問→本文→根拠の往復

基礎が整ったら、点につながる読み方に落とします。長文は全部理解より設問に答える。
そのための手順を固定するだけで、正答率と時間配分が安定します。ここでは、難易度を問わず通用する流れだけを残します。まず設問を先にざっと見て、問われ方(内容一致/語句補充/指示語/下線部説明)を頭に置く。本文は段落の最初と最後を丁寧に、中はチャンクで滑らせながら“どの設問のヒントか”を心の中でタグ付け。迷ったら戻る。根拠が線で拾えていれば、選択肢の迷いは短くなります。
それでも詰まったら
どうしても進まない日は、問題演習を止めて基礎の3本に戻る。かたまり読み10文、コア語彙10語、音読とシャドー10分。これで一度リセットしてから翌日に再挑戦。伸びないのは才能ではなく、回復の順番がズレているだけ。焦らず、でも止まらず。
まとめ

英語長文が読めないと感じるときは、
1)前からかたまりで読む(語順の流れ)
2)コアの意味とコロケーションで語彙を立体化する
3)音で前から処理する回路を作る
の三つに立ち返るのが最短です。基礎が整えば、設問→本文→根拠の往復が苦なく回り、時間切れも減っていきます。今日の10分が、来週の“読めた”に直結します。派手さはないけれど、毎日少しずつ流れを良くする。長文は筋トレです。続けた分だけ、目が前へ進むようになります。