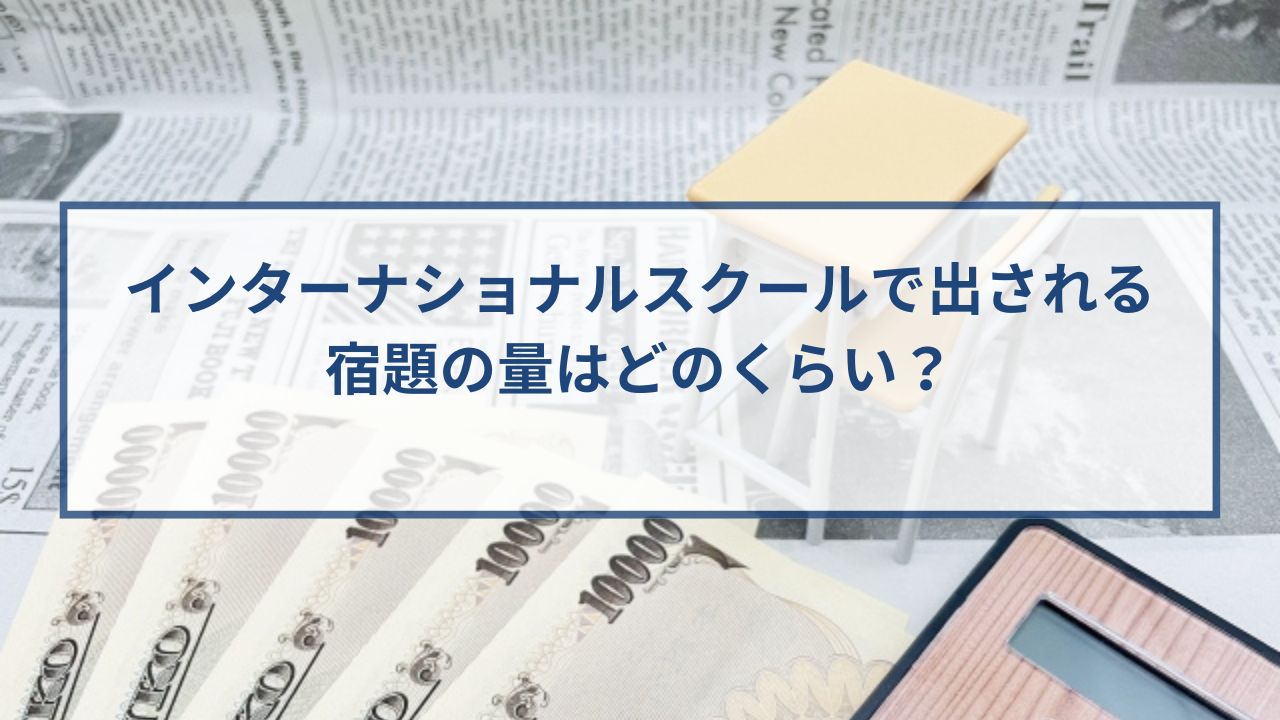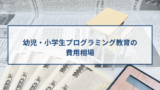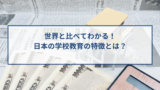インターナショナルスクールを検討する際、親御さんがまず注目するのは学費やカリキュラムですが、実際に通わせる場面を想像すると「宿題はどのくらい出るのだろう?」という疑問が浮かぶことが少なくありません。日本の公立小学校では、学年ごとに宿題の量や内容がある程度決まっており、漢字ドリルや計算練習のような反復学習が中心です。しかしインターナショナルスクールの場合、そのアプローチは大きく異なります。
「子どもが毎日数時間も宿題に追われて疲れてしまわないか」「英語で出される課題にきちんと取り組めるのか」など、親御さんの心配は尽きません。ただ実際には、宿題の量や質は「子どもに学びを楽しませ、考える力を育てる」という観点から設計されています。つまり、日本的な「こなす宿題」よりも「探究を促す宿題」が多いのです。
本記事では、インターナショナルスクールにおける宿題の特徴や学年ごとの目安、日本の学校との違い、さらに親としてどのようにサポートできるかを丁寧に解説します。
インターナショナルスクールの宿題の特徴とは?

宿題と一口にいっても、その中身は学校や教育方針によって大きく違います。インターナショナルスクールでは特に「量より質」が重視されている点が、日本との大きな違いです。
反復よりも「考える力」重視
日本の学校では「同じ計算を10回繰り返す」「漢字を何度も書いて覚える」といった反復型の宿題が主流です。もちろん基礎力をつける上では重要ですが、インターナショナルスクールではそれ以上に「なぜそうなるのか」「どう説明するか」といった思考力や表現力を伸ばす課題が中心になります。
例えば「植物の成長を観察して、その過程を絵や文章で表現する」「読んだ本の中で自分が一番共感した場面を理由と一緒に説明する」といった内容です。正解を出すことよりも「どう考えたか」を大切にする姿勢が根付いています。
プロジェクト型の課題
インターナショナルスクールでは、宿題が単発で終わらず「数週間かけて取り組むプロジェクト課題」として出されることも珍しくありません。例えば「身近な環境問題を調べてプレゼンを作る」「好きな国についてリサーチして文化を紹介する」といった課題です。子どもは自分で調べ、まとめ、発表する過程を通して、リサーチ力やプレゼン力を養います。
家庭との関わりを重視
もう一つの特徴は「宿題が家庭とのコミュニケーションのきっかけになる」よう設計されている点です。例えば「家族にインタビューしてレポートを書く」「家庭でよく使う英語のフレーズをリスト化する」といった課題です。こうした宿題は、家庭の中で学びを共有する時間を生み出し、子どもが「学びは学校だけでなく生活全体につながっている」と実感できる仕掛けになっています。
宿題の量はどのくらい?学年別の目安は?

「宿題の質」が違うことは分かっても、親御さんとしては「1日にどのくらい時間がかかるのか」がやはり気になるポイントです。学校やカリキュラムによって幅がありますが、おおよその目安を学年ごとに紹介します。
幼児・低学年(プリスクール〜小学校低学年)
この時期は「宿題=学習習慣を作る」ことが目的で、量はごくわずかです。1日10〜20分程度で終わる課題が中心で、絵本の音読、アルファベットの練習、親と一緒に簡単な単語を使うといった内容が多いです。宿題というより「遊びに近い学び」と考えた方がイメージに近いでしょう。
中学年(小学校中学年)
学習の幅が広がり、宿題も30分〜1時間程度に増えます。リーディングやライティングだけでなく、理科や社会に関連するリサーチ課題も出されるようになります。例えば「地元の植物を観察して記録し、英語でまとめる」といった宿題です。興味を持ちながら知識を広げられるよう工夫されています。
高学年(小学校高学年〜中学生)
1〜2時間程度かかる宿題が一般的になります。単純な宿題よりも、プロジェクト型やグループ課題が増え、協力してまとめる作業も含まれることがあります。例えば「国連で取り上げられている課題について調べ、自分の意見をまとめる」といったタスクです。授業の延長として「学びを深める宿題」が増える時期です。
高校生
高校では宿題は大学進学を意識した内容にシフトします。毎日のリーディング課題やエッセイに加え、IB(国際バカロレア)やAP(アドバンスト・プレイスメント)といったプログラムに対応する高度な課題も多くなります。2〜3時間以上かかることも珍しくなく、専門的な研究やレポート作成が日常的に課されることもあります。
日本の学校との違いとは?

宿題の量や質をより具体的に理解するためには、日本の学校と比べてみるのが分かりやすいです。
宿題の目的の違い
日本の学校では「基礎学力を定着させること」が中心ですが、インターナショナルスクールでは「自分で考える力を育てること」が目的です。同じ宿題でも「正解に早くたどり着く」より「どうやって考えたか」を評価される点が大きく違います。
家庭学習のスタイル
日本では「宿題は一人でこなすもの」という文化がありますが、インターナショナルスクールでは「親や家族と一緒に取り組む宿題」も出されます。家族で調べたり、会話を通じて学ぶことを大切にしているのです。
成績評価への影響
日本の学校では「提出したかどうか」が評価に直結することもありますが、インターナショナルスクールでは「どのように取り組んだか」が重視されます。完成度そのものよりも、工夫や姿勢を見て評価する文化があります。
宿題への向き合い方と親のサポート

宿題を前向きな学びにするためには、親のサポートが欠かせません。
無理に手を出さない
子どもが難しさを感じていると、つい答えを教えたくなりますが、インターナショナルスクールの宿題は「調べ方を学ぶ」こと自体が目的です。わからないときは一緒に調べるサポートをする程度にとどめ、子ども自身が答えを見つけられる環境を整えるのが理想です。
環境を整える
宿題に集中できる環境を整えるのは大切です。リビングの一角や静かな部屋など、子どもが落ち着いて学べる場所を用意してあげると取り組みやすくなります。また「宿題の時間」を毎日一定にすると習慣づけやすいです。
ポジティブな声かけ
宿題を「やらなければならない作業」と思わせず「成長のチャンス」と感じられるように声かけすることが重要です。「ここまでできたね」「昨日よりスムーズになったね」といった小さな成長を認めてあげることが、子どもの自信につながります。
まとめ

インターナショナルスクールの宿題は、日本の学校とは大きく異なります。低学年では短時間で終わる課題から始まり、中高学年ではリサーチやプレゼンを中心とした探究型の宿題が増え、高校では大学進学を見据えた本格的な課題に発展します。
どの段階でも共通しているのは「宿題を通じて考える力や主体性を育てる」という点です。量だけを比べれば日本より多く感じる場面もありますが、それは「ただこなす宿題」ではなく「学びを深める宿題」であるからです。
宿題への不安は自然なことですが、親としては「どんな力を育てる宿題なのか」を理解しておくことが安心につながります。そして、時には一緒に調べたり、前向きな声かけをすることで、宿題は子どもにとって「学びの喜びを広げる入り口」になるでしょう。