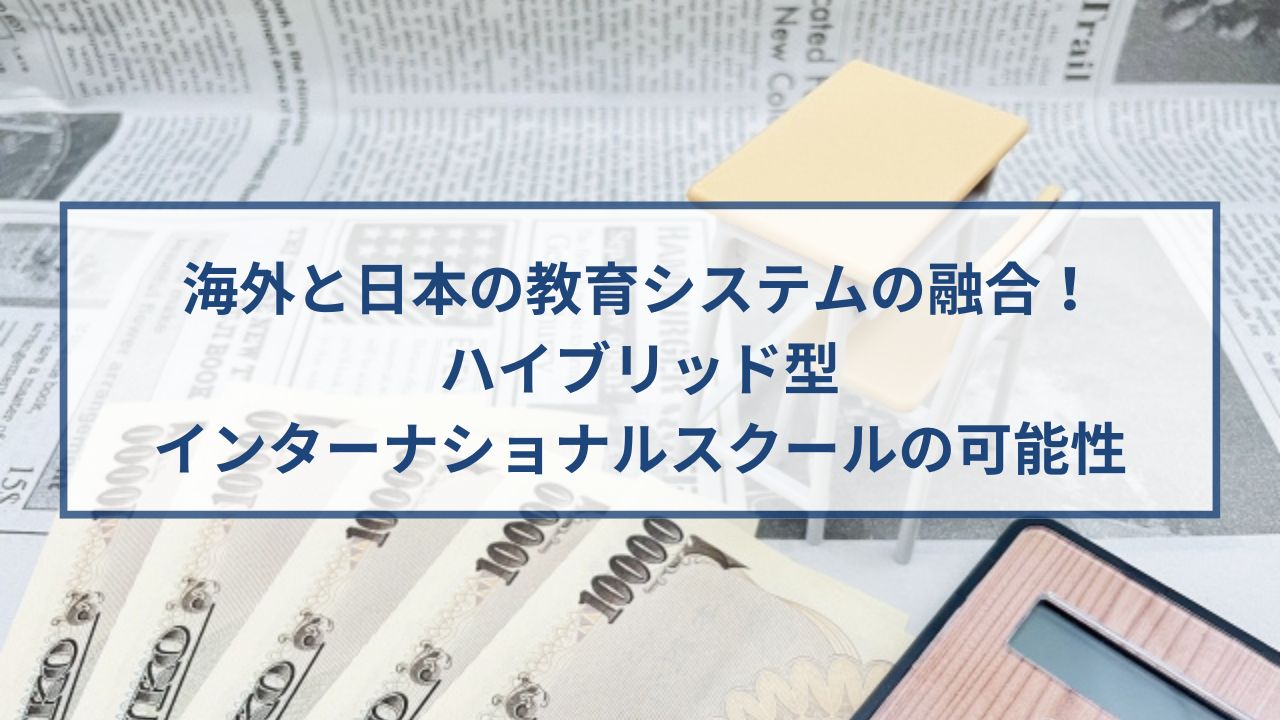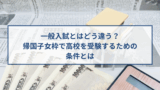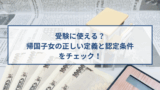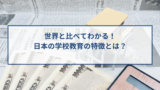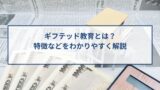「英語も大事、でも日本語力も捨てたくない」
「自己表現も伸ばしてほしいけど、協調性も育てたい」
そんなふうに、子どもの教育に対して“バランス”を重視する親御さんが増えてきています。
実際、「インターナショナルスクール」と聞くと、「自由な校風」「英語力重視」「海外式教育」というイメージを持たれる方も多いかもしれません。けれど、いざ具体的にどんな教育が行われているのか、何を大切にしているのか、情報があいまいで「ピンとこない」という声も少なくありません。
一方で、最近注目されているのが、ハイブリッド型のインターナショナルスクール。
これは、従来の海外式教育の長所に加えて、日本の文化や教育観にも一定の価値を置きながら設計された、新しいタイプのスクールです。
・海外式の自由で探究的な学び
・日本的なきめ細かい配慮や生活指導
・母語(日本語)を育てるバイリンガル教育
こうした両方の要素を柔軟に取り入れるスタイルが、「子どもに合った学びを届けたい」と願う親御さんたちの間で支持されつつあります。
この記事では、そんなハイブリッド型インターナショナルスクールの教育システムにフォーカスして、教育方針や日本の学校との違い、通わせているご家庭の声などをもとに、未来志向の学びのあり方を探っていきます。
インターナショナルスクールの教育システムとは?

「インターナショナルスクール」とひとことで言っても、その中身はさまざま。実は、学校によってカリキュラムや教育方針は大きく異なります。
中でもよく導入されているのが、以下のような国際的な教育プログラムです:
- 国際バカロレア(IB):探究型の学びと国際的な視点を重視するカリキュラム。年齢に応じた「PYP(初等)」「MYP(中等)」「DP(高等)」の3段階がある。
- ケンブリッジ国際カリキュラム:英国の教育体系に基づいた、評価基準と内容が明確なプログラム。
- アメリカ式カリキュラム:リベラルアーツ的なアプローチが特徴で、多様性を尊重しつつ、個性を伸ばす教育がベース。
こうしたカリキュラムに共通しているのは、「暗記より思考」「知識より探究」「指導より対話」を重んじる点。生徒が自分の意見を持ち、それを表現し、異なる価値観と出会っていく力を育てる教育がベースにあります。
たとえば、あるIB導入校では、「水」をテーマにしたユニット学習で、世界の水資源や衛生問題について自分たちで調べ、プレゼンし、ポスター展示を企画したそうです。ただ「水について学ぶ」だけでなく、「社会と自分の関係」まで考えるのがこの教育の特徴です。
一方で、こうした教育に初めて触れる親御さんの中には、次のような不安を抱くケースもあります。
- 「日本の授業のように一斉指導じゃないと、ついていけないのでは…?」
- 「自由な雰囲気すぎて、社会に出たときギャップが大きくなりそう」
- 「英語は伸びそうだけど、日本語が弱くなってしまわない?」
こうした心配は、ごく自然なものです。なぜなら、日本の学校とは教育観やスタイルそのものが違うから。
しかしその違いこそ、インターナショナルスクールの教育システムを理解するうえでの出発点なのです。
次のセクションでは、その違いを「日本の教育観」と比較しながら、より具体的に掘り下げていきます。
日本の教育とどう違う?価値観のすれ違いに戸惑う声も

「海外式教育って、なんだか自由すぎる気がするんです」
「みんなで一緒にやる日本式の方が、社会性は育ちそうで…」
インターナショナルスクールを検討している親御さんの中には、そんな声を漏らす方も少なくありません。
これは、どちらが正しいという話ではなく、教育における価値観の違いから生まれる感覚です。
日本の教育は、どちらかというと調和を重視します。
- 全員が同じことを同じようにできる
- 足並みをそろえる
- 空気を読む
- 先生の話をきちんと聞く
一方で、海外式の教育では、個の発信力や思考の深さを大切にする傾向があります。
- 「なぜそう思うのか?」を言葉にする
- 違いを肯定する
- 話し合いやプレゼンが頻繁にある
- 一人ひとりの理解の深さに合わせて進める
つまり、教育のゴールの置き方が根本的に違うのです。
たとえば、算数の授業ひとつを取っても、日本では「先生が黒板に書いた方法をみんなで習う」が基本ですが、海外式では「この問題、みんなならどう解く?」と問いかけからスタートし、子どもたちが自分のやり方を見つけてシェアするという流れが一般的です。
この違いは、最初は戸惑いを生みやすいですが、同時に子どもたちの中に「学びは他人から与えられるものではなく、自分でつかむもの」という意識を育ててくれます。
もちろん、日本の教育にも素晴らしい点がたくさんあります。丁寧さ、礼儀、勤勉さ、集団意識など、社会に出たときに必要な素地は日本式教育に多く含まれています。
だからこそ、次にご紹介する「ハイブリッド型」のアプローチが注目されているのです。
ハイブリッド型インターナショナルスクールとは?

ハイブリッド型インターナショナルスクール。
最近、この言葉を耳にする機会が増えたという親御さんもいるかもしれません。
簡単に言えばこれは、「海外式の教育カリキュラム」と「日本的な教育観・生活文化」をバランスよく融合させた新しいスクールモデルです。
たとえば、ある東京のハイブリッド型インターナショナルスクールでは、以下のような特徴的な取り組みがなされています。
- 国際バカロレアPYPを導入しつつ、日本語での探究学習も必須に
- 校内での生活指導はあいさつ・整理整頓・協調を重視
- 年齢が低いうちは英語と日本語の比重を均等に保ち、言語の偏りを防ぐ
- 道徳の授業では思いやりや周囲を気遣う心を日本語で学ぶ時間も設置
つまり、カリキュラムはグローバルだけれど、育てる子どもの姿には日本的な価値もちゃんと含まれているんです。
このスタイルの利点は大きく分けて3つ:
- アイデンティティの形成:母語である日本語も大切にすることで、「自分は何者か」という軸がしっかり育つ
- 社会適応力の強化:日本社会での振る舞いを理解したうえで、グローバルな視点も持てるようになる
- 多文化への順応性:異文化と接する準備期間として、急な文化の変化に戸惑わずに済む
完全な海外スタイルに不安を感じる家庭にとって、このハイブリッド型は、安心と挑戦のちょうどよいバランスを提供してくれる新しい選択肢だと言えます。
実際に通わせている親御さんの声から見えるリアル

「自由すぎて不安だったけど、子どもの表情が変わった」
「話すのが苦手だったうちの子が、堂々とプレゼンするようになって驚きました」
こうした声は、実際にハイブリッド型インターナショナルスクールに子どもを通わせているご家庭から多く聞かれます。
あるお母さんは、最初は「日本の学校の方が安定しているのでは」と考えていたそうです。でも説明会で出会ったのは、学校と親が一緒に育てていくというスタンスを大切にしているスタッフや先生たちでした。
実際に通わせてみて感じた変化は次の3つだったと言います:
- 子どもが「わかってもらえる場」で前向きになったこと
- 正解を当てることより、「自分の考え」を言えるようになったこと
- 失敗を恥ずかしがらず、「やってみる」姿勢が育ったこと
親御さんの声を通して見えてくるのは、「ハイブリッド型だからこそ得られる中庸性」と「柔軟な教育環境」が、子どもに安心と挑戦のバランスをもたらしているということです。
もちろん、最初からスムーズにいくとは限りません。家庭でのフォローや、スクールとの連携も重要です。でも、それでもなお「選んでよかった」と感じるのは、子どもの内側に起きた目に見える変化があったからこそ。
インターナショナルスクールを選ぶか、日本の学校にするか。
それは単なる場所の違いではなく、子どもにどんな力を育んでほしいかという価値観の選択です。
海外式には、個性と探究の力があり、
日本式には、丁寧さと協調の力がある。
どちらかを否定する必要はありません。
そして今、「その両方を育てる」という道も、確かに広がってきています。
ハイブリッド型インターナショナルスクールは、そんなバランスを大切にしたいという想いに応える、新しい学びの場です。
選択肢が増えた今だからこそ、「自分たちの子育て観」を見つめ直す時間を、ほんの少し持ってみてもいいのかもしれません。