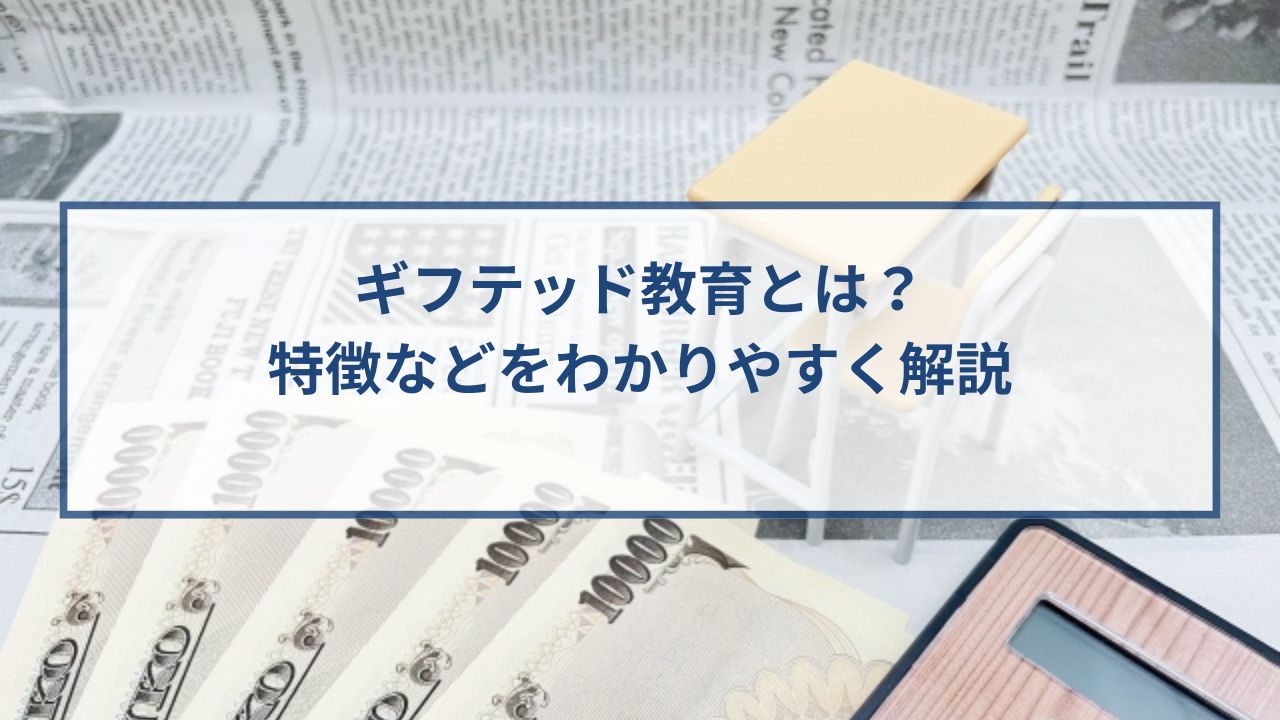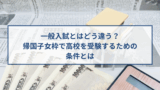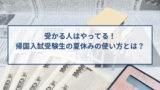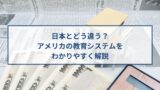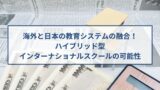「授業についていけない、というより遅くて退屈って言うんです…」 「興味が偏ってて、周りにうまく馴染めなくて…」
もし、そんな悩みを感じたことがあるなら、もしかすると「ギフテッド教育」という選択肢がヒントになるかもしれません。
ギフテッドというと、何か特別な才能に恵まれた天才のようなイメージがあるかもしれませんが、実は「認知の仕方が違う」「刺激への感度が強い」など、多様な特性を持つ子どもたちを指すことが多くあります。
そしてその子たちは、通常の教育環境では力を発揮できず、むしろ不安や孤独を抱えてしまうことさえあるのです。
だからこそ、ギフテッド教育は「飛び級」や「英才教育」だけではなく、子ども一人ひとりにとって心地よく学べる環境を探るアプローチとして、いま再注目されています。
ギフテッドってどんな子?

ギフテッドとは、ざっくり言うと「何らかの分野において顕著に高い能力をもつ子ども」を指します。
一般的にはIQ130以上などの基準が挙げられることが多いですが、実際にはそれだけではありません。次のような特徴をもつことが多くあります:
- 興味のあることに対して驚異的な集中力を発揮する
- 感受性が非常に強く、周囲の刺激や人の感情に敏感
- 言語能力や論理的思考が年齢よりも突出して高い
- 一方で、感情のコントロールや集団生活に苦手意識がある
- 一部の分野に極端なこだわりがある(例:恐竜、宇宙、元素記号など)
つまり、ただ「頭がいい」わけではなく、「興味のアンバランスさ」や「社会性のズレ」を感じることも少なくないのです。
たとえば、小2で高校レベルの英語を読めるけど、算数の計算は苦手といったケースや、授業中はぼーっとしているのに、宇宙の話だけは目が輝くといった様子など。
親御さんにとっては、学校の成績や周囲の評価と我が子の様子のギャップに、戸惑いを感じることもあるかもしれません。
でも、そんなちょっと変わった特性こそが、ギフテッドのサインかもしれないのです。
次の章では、ギフテッド教育がどんな学び方を提供しているのかを見ていきましょう。
ギフテッド教育って何をするの?

ギフテッド教育の最大の特徴は、その子が興味を持った分野をとことん伸ばすという点にあります。
一般的な教育では、すべての教科をバランスよく学ぶことが求められますが、ギフテッド教育では、あえて尖った部分を尊重するのです。
たとえば、
- 理系に強い子どもに対して、大学レベルの科学や数学の探究機会を提供
- 文系や語学に突出した子に、プレゼン・エッセイ・ディベートを深める授業を用意
- 芸術分野に感性をもつ子には、自由な創作の場や個展発表のチャンスを用意
こうした「飛び級」「個別カリキュラム」「専門家との学び」などは、アメリカやカナダ、オーストラリアなどで広く取り入れられています。
一方で、ギフテッドの子どもたちはその強さゆえに、自己肯定感が揺らぎやすい傾向もあります。
「みんなと違うこと」が、誇らしさではなく孤立や違和感につながってしまうこともあるからです。
だからこそ、ギフテッド教育では学問的な伸長だけでなく、
- 同じ特性をもつ仲間と出会えるコミュニティ
- 感情面・社会面のサポート(SEL:社会性と情動の学習)
- 子ども自身が「理解されている」と感じられる環境づくり
が、セットで重視されています。
つまり、ギフテッド教育とは「飛び級して先に行く」ことではなく、 「その子の興味や特性に合わせた学びを、安心できる場で支えること」と言えるのです。
では実際、親としてギフテッド教育にどんな関わり方ができるのでしょうか? 次の章では、家庭でのサポートのヒントをお伝えします。
家庭でできる関わりとは?

ギフテッドの子どもたちは、家庭でも扱いにくさを感じる場面が少なくありません。
・些細な音や光に過敏に反応する(感覚過敏) 、言葉が早く、質問が止まらない(知的好奇心) 、完璧主義で、失敗を極端に嫌う(自己評価の高さ) 、友達との関係がうまくいかず、孤立感を持ちやすい。
そんなとき、「普通にしてほしい」「周りに合わせて」と言いたくなる気持ちは、親として当然のこと。
でも実は、普通の子育てがうまくいかないからこそ、ギフテッド教育という視点が必要とされるのです。
親御さんができる関わりとしては、たとえばこんな方法があります:
- 子どもの興味を否定せず、「どうしてそれが好きなの?」と丁寧に聞く
- 「変わってていい」と日常的に伝えることで、“安心の土台”をつくる
- 本人の中の“できない部分”にも目を向け、「全部が得意なわけじゃない」とバランスを取ってあげる
- 同じ特性を持つ子どもたちが集まる外部の教室やオンライン講座を活用する
何より大切なのは、「親がわかってくれる」と子どもが感じられることです。
ギフテッド教育は、専門家や制度の力も大切ですが、家庭の中でわかってもらえる安心感があるかどうかで、その効果がまるで違ってくるのです。
では最後に、「ギフテッド教育って結局どう考えればいいの?」という疑問へのヒントとして、締めくくりをしていきます。
「うちの子、ちょっと変わってるかも」「まわりに合わせづらそう」「すごく得意なことが一つだけある」そんなふとした気づきが、ギフテッド教育という選択肢につながることがあります。
でも、ギフテッドというラベルに縛られてしまうと、本来の目的を見失ってしまうこともあるのです。 大切なのは、「この子にはどんな学びの形が合っているか」を一緒に考えていく姿勢。
たとえ特別な学校に通わなくても、日々の生活の中でその子の“好き”や“得意”を尊重すること、時に「周囲と違う自分」を受け止めてくれる大人がいること。 それだけでも、子どもは安心して自分の道を切り拓いていけます。
ギフテッド教育は、特別な子のためだけのものではありません。 一人ひとりの子どもが、自分らしく学び、成長できるようにするためのひとつのアプローチです。
もし今、わが子の育ち方や学び方に悩んでいたり、もやもやを感じているとしたら、 その感覚こそがきっと、はじめの一歩になるはずです。
「ギフテッド教育」という選択肢を知った今、親としてできることはきっと少なくありません。 子どもの声に耳を傾けながら、必要なタイミングで必要な環境を選び取れるよう、少しずつ視野を広げていきましょう。