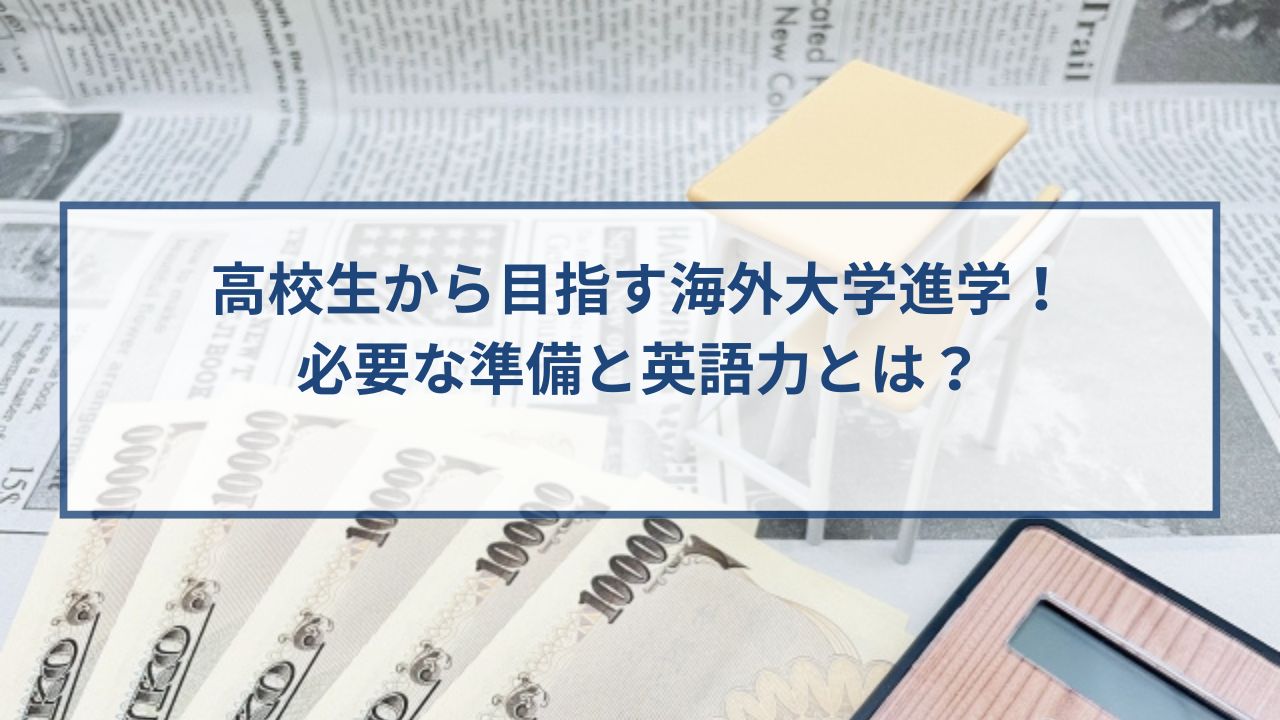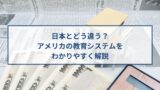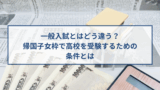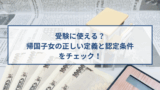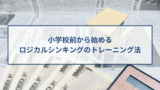「海外の大学って、やっぱりすごく難しいのかな…」 「英語力だけじゃダメって聞いたけど、何を準備したらいいの?」
そんなふうに感じている高校生、多いかもしれません。 日本の大学とはまったく異なる出願方式、求められるスキル、そして自分らしさが問われるエッセイ。
でも、「世界に飛び出してみたい」「視野をもっと広げたい」そんな気持ちがあるなら、それはもう立派な第一歩です。
海外の大学進学は、誰か特別な人だけの話ではありません。 情報と準備の方向性さえ間違えなければ、確実にチャンスをつかむことができます。
このページでは、これから海外の大学を目指そうと思っている高校生に向けて、必要な力・準備・心構えをわかりやすくまとめていきます。 まずは、そもそも「海外の大学ってどんな特徴があるのか?」というところから一緒に見ていきましょう。
そもそも日本と何が違う?

日本では「偏差値」「試験の点数」で進学先が決まりがちですが、たとえばアメリカやイギリス、カナダなどの大学では、学力だけでなく「自分の考え」「興味の深さ」「社会への関心」などが問われます。
つまり、試験の点数よりも自分自身をどう表現するかが大きな鍵になってくるのです。
実際に、アメリカの大学では授業中に発言することが当たり前で、「自分の意見を持っているか」「相手の意見を聞けるか」が日常的に試されます。 課題もリサーチエッセイやプレゼンテーションが多く、「覚える学び」から「伝える・考える学び」へと変わっていくのが特徴です。
たとえば、ハーバード大学の1年次必修科目のひとつ「Expository Writing」は、自分の主張を明確に構成しながら文章で伝える力を徹底的に鍛えます。
このような背景から、海外大学への進学を考えるなら、「英語のスキル」だけではなく、日頃から考えて、表現する経験を積むことが大切になってきます。
出願に必要な準備

海外大学の出願は、「試験を受けて合格発表を待つ」という日本のスタイルとは大きく異なります。
必要とされる要素は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のような準備が求められます。
① 高校の成績(GPA)
最も基本となるのが、高校での成績=GPA(Grade Point Average)です。
アメリカなどの大学では、内申点をベースに「どの教科をどれだけ頑張ってきたか」が評価されます。
つまり「普段の授業をどれだけ真剣に受けてきたか」が問われるんです。
例えば、オール5の成績であれば、日本の上位国立大学に出願するのと同等レベル。特に11年生(高2)から12年生(高3)の成績が重視されるため、早めの意識が重要です。
② 英語力の証明(TOEFLやIELTS)
留学生として出願する場合、英語での授業に耐えうる能力があることを証明しなければなりません。
その代表的な試験が「TOEFL iBT」と「IELTS」です。
たとえば、カリフォルニア大学バークレー校ではTOEFL iBT 100点以上が目安とされており、これは英検1級にも匹敵する難易度。
「留学するには英語がネイティブ並じゃないと無理」と感じるかもしれませんが、実際には段階的に対策できるものです。
高1〜高2のうちに受験経験を積んでおくと、慣れと目安がつかみやすくなります。
③ SAT/ACTなどの共通テスト(主にアメリカ)
アメリカの大学に出願する際に使われる「SAT」や「ACT」といった試験もあります。
日本のセンター試験に近い位置づけですが、これらは学力というよりも「論理力」や「英語での思考力」を見るもの。
ただし、近年はハーバード大学やスタンフォード大学など、こうした試験の提出を“任意”としている大学も増えており、「自分の強み」で勝負できる仕組みになってきています。
④ 課外活動・リーダーシップ経験
成績や試験だけでなく、学外でどんな活動をしてきたかも非常に重要です。
生徒会、ボランティア、部活動のキャプテン、NPOでの活動。こういった実績が、「この子は自分の考えを行動に移せる子だ」と評価されるポイントになります。
特にアメリカの大学は「リーダーシップ」「社会貢献」「創造性」を重視するため、ただのお勉強ができる子ではなく、「どんな人間性を持っているか」が問われます。
⑤ パーソナルエッセイ(志望動機と自己表現)
最大の山場といってもいいのが、出願時に提出する「パーソナルエッセイ」です。
ここでは、「なぜこの大学に行きたいのか」「自分はどんな人間なのか」を、英語でしっかりと書き表す必要があります。
たとえば「これまでの経験から何を学び、それをどう生かしたいか」といった視点で、自分だけの物語を綴ります。
添削指導を受けながら、何度も書き直して完成度を高めるのが一般的で、1本のエッセイに数ヶ月かける受験生も少なくありません。
こうして見ると、「どれもこれも完璧じゃないと無理なのでは…」と不安になるかもしれませんが、大丈夫です。
すべてが100点満点である必要はありません。
実際には、「成績はそこそこだけど課外活動がすごい」「英語はまだまだだけどエッセイがめちゃくちゃ光ってる」など、自分らしい強みを見つけて伸ばしていくスタイルが海外進学です。
次のセクションでは、そんな準備を進める中での親御さんの関わり方や家庭でできるサポートについて、一緒に考えてみましょう。
親のサポートや心構え

海外大学進学を目指すには、子ども自身の努力はもちろんですが、親御さんの理解とサポートが大きな力になります。
「何をどう応援すればいいのか分からない…」と感じることもあるかもしれません。ですが、完璧なアドバイザーになる必要はありません。
大切なのは、子どもが迷ったときに“戻れる場所”としてそばにいてあげることです。
たとえば、エッセイがなかなか進まないときや、TOEFLの点数に伸び悩んでいるとき。
親御さんの「じゃあ今日は気分転換しようか」「一緒に計画を見直してみようか」といった声かけが、子どもにとっては大きな支えになります。
また、情報収集の面でも、子ども任せにせず、一緒に大学のWebサイトを見たり、海外進学セミナーに参加したりすることは、「自分はひとりじゃない」と感じられる大きな後押しになります。
親御さんが留学経験者でなくても構いません。むしろ、「わからないけど、一緒に知っていこう」という姿勢こそが、子どもの安心感とチャレンジ精神を引き出すのです。
さらに、進学先の国や大学の文化、生活環境などについても、家庭内で対話できると理想的です。
「アメリカの大学って、寮生活が基本らしいよね」 「イギリスだと、3年制で専門的に学ぶんだって」
そんな何気ない会話が、子どもにとっては“将来のイメージ”を形づくるヒントになります。
進学先での暮らしを親子で一緒に想像しておくことは、不安をやわらげるうえでも非常に大切です。
逆に注意したいのは、無意識にプレッシャーをかけてしまうケースです。
「せっかくやるなら、絶対に合格してね」
「英語が苦手じゃ、海外大学は無理じゃない?」
こういった言葉は、子どもの自己肯定感を下げてしまう原因にもなりかねません。
期待ではなく信頼を。応援ではなく伴走を。
そのスタンスこそが、海外進学を志す子どもにとって、何より心強い土台になると私は思います。